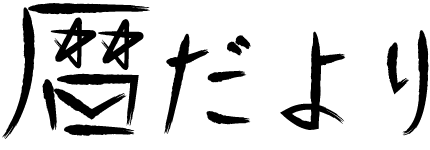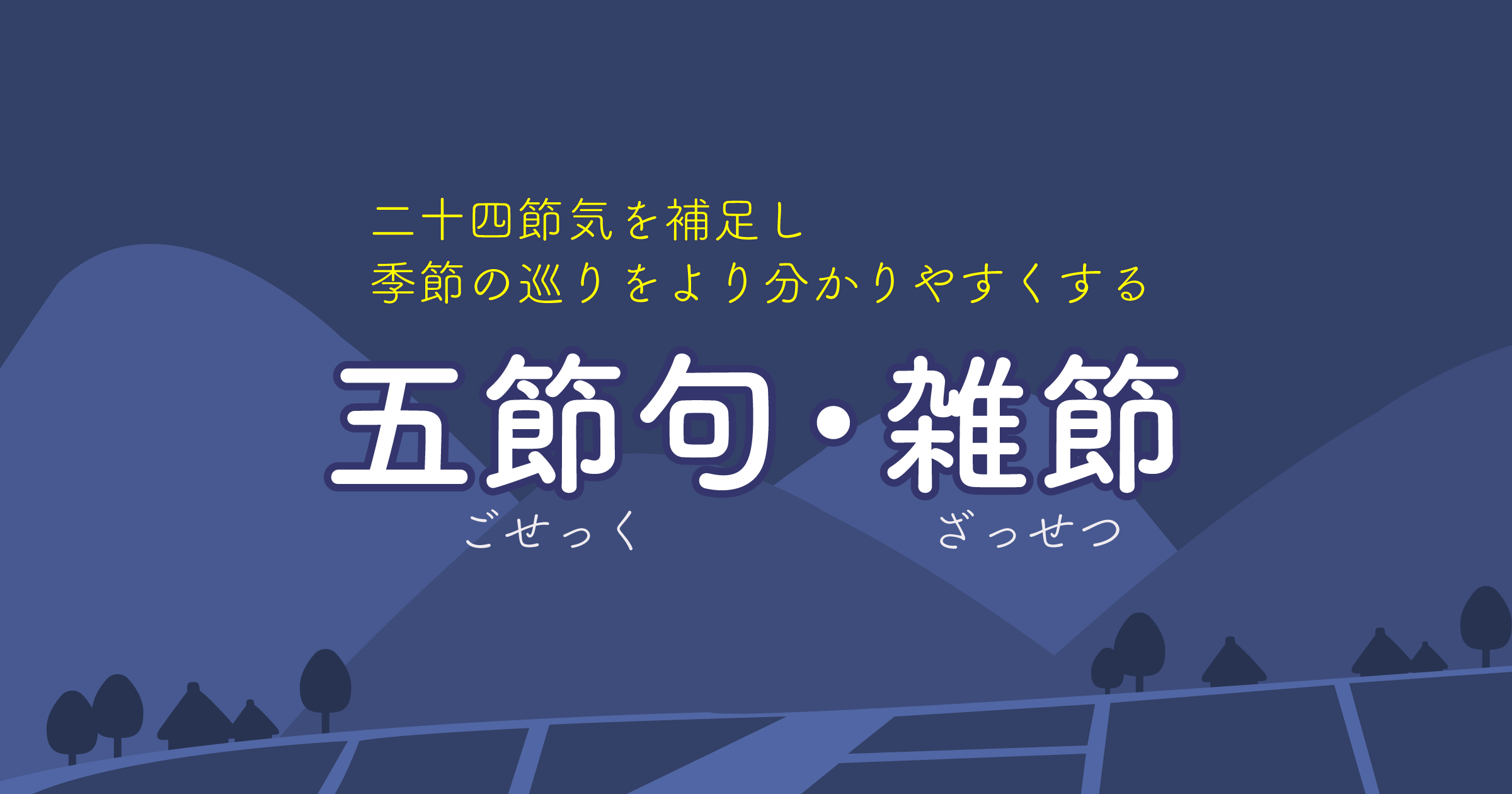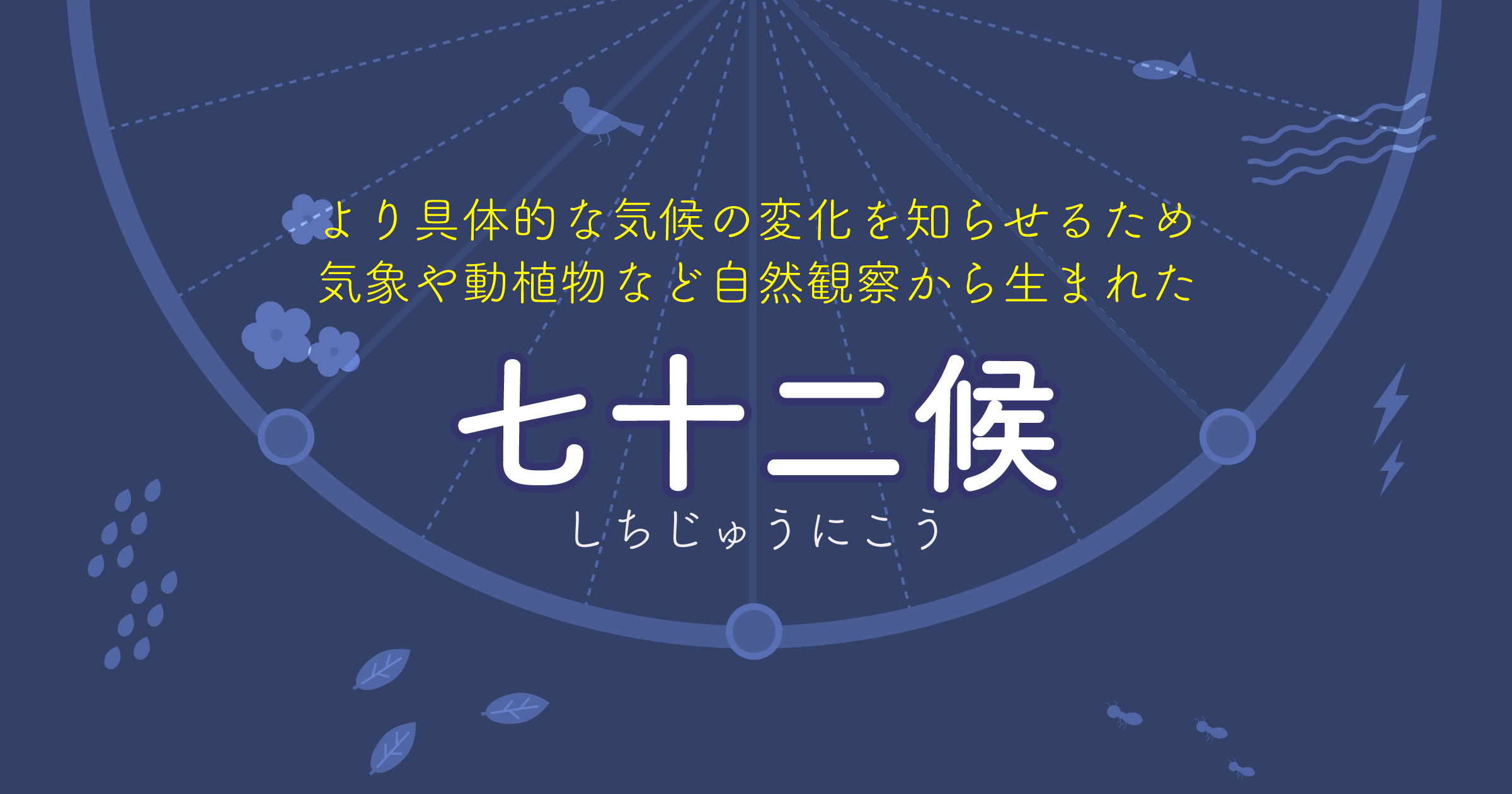五節句とは
五節句は、二十四節気のように季節の移ろいを把握するのに便利な暦日です。
中国では、奇数が重なる日は縁起が悪いとされていました。そのため、季節の旬の植物から生命力を分けてもらって邪気を払うとされた日です。
日本では宮中で邪気払いの宴会が催されたり、農村の風習と合わさったりして「節句」となりました。江戸時代には公的な祝日として制定されましたが、明治6年に新暦が採用されたときに廃止となり、その後は年中行事として定着しています。
新暦に変わったことで、五節句は季節とのズレが生じるようになってしまいました。そのため地方によっては「月遅れ」といって一ヶ月遅い日付でおこなうところもあります。
五節句一覧
雑節とは
雑節とは、二十四節気と五節句のほかに、季節の移ろいの目安となる日の総称です。
二十四節気だけでは季節の変化が読み取りづらいとして、農作業に従事する人たちによって新たに考案され、二十四節気を補足するのものとして重要視されました。
雑節一覧
| 節分 | (せつぶん) 2月3日頃。立春の前日。 |
| 彼岸 | (ひがん) 春分(3月21日頃)または秋分(9月23日頃)をはさんだ前後3日ずつの7日間。初日を彼岸の入り、当日を中日、終日を明けと呼ぶ。 |
| 社日 | (しゃにち) 春分または秋分に最も近い「戊」の日。1年に2回。 |
| 八十八夜 | (はちじゅうはちや) 5月2日頃。立春から数えて88日目。 |
| 入梅 | (にゅうばい) 6月11日頃。二十四節気「芒種」の後の「壬」の日から31日間とされる。 |
| 半夏生 | (はんげしょう) 7月2日頃。夏至から11日後。 |
| 土用 | (どよう) 元々は立春・立夏・立秋・立冬の前の18日間。 |
| 二百十日 | (にひゃくとおか) 9月1日頃。立春から数えて210日目。 |
| 二百二十日 | (にひゃくはつか) 9月11日頃。立春から数えて220日目。 |