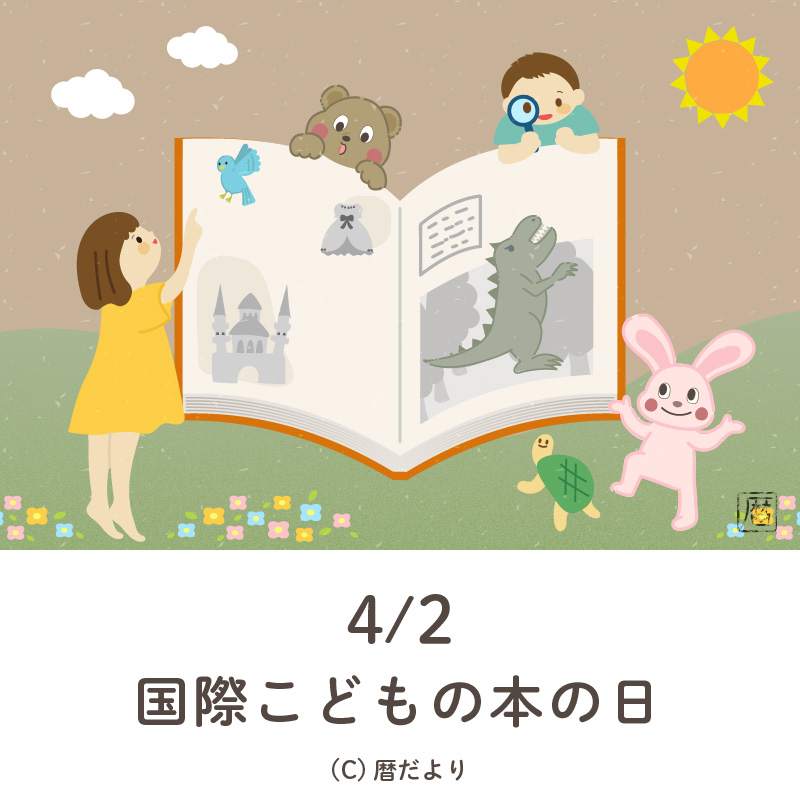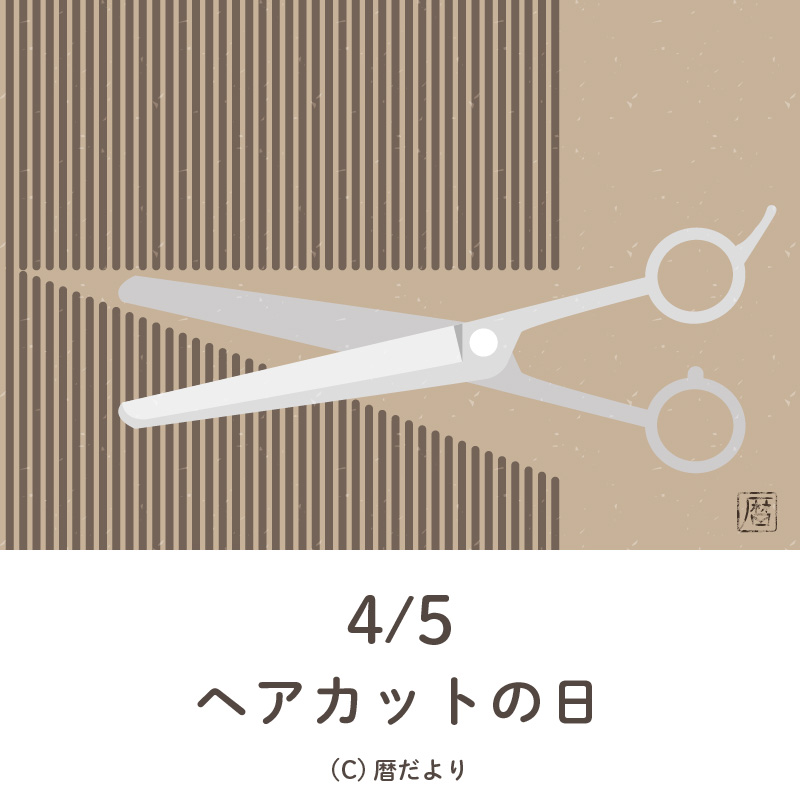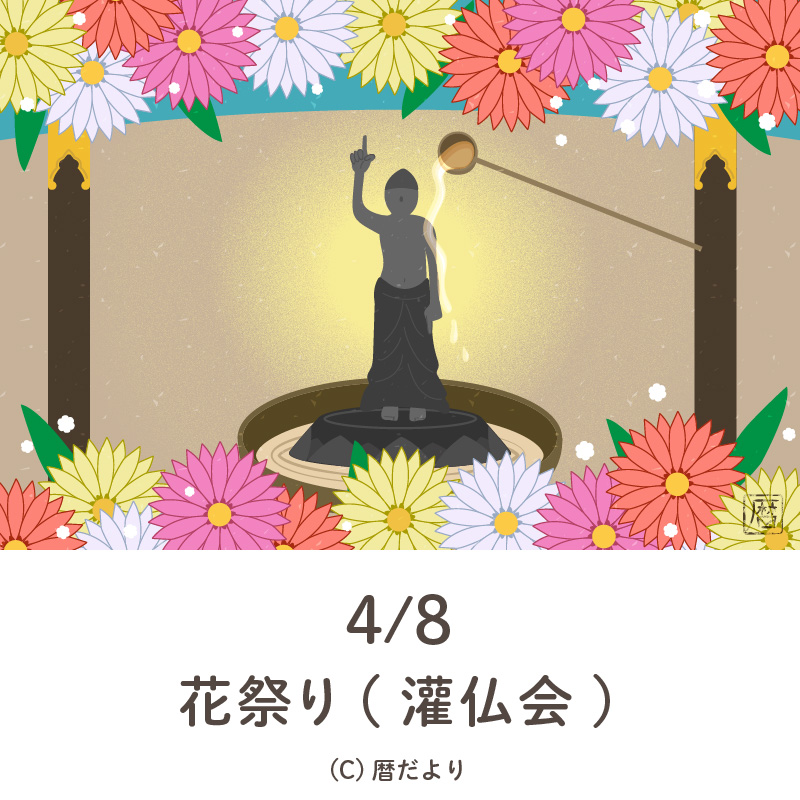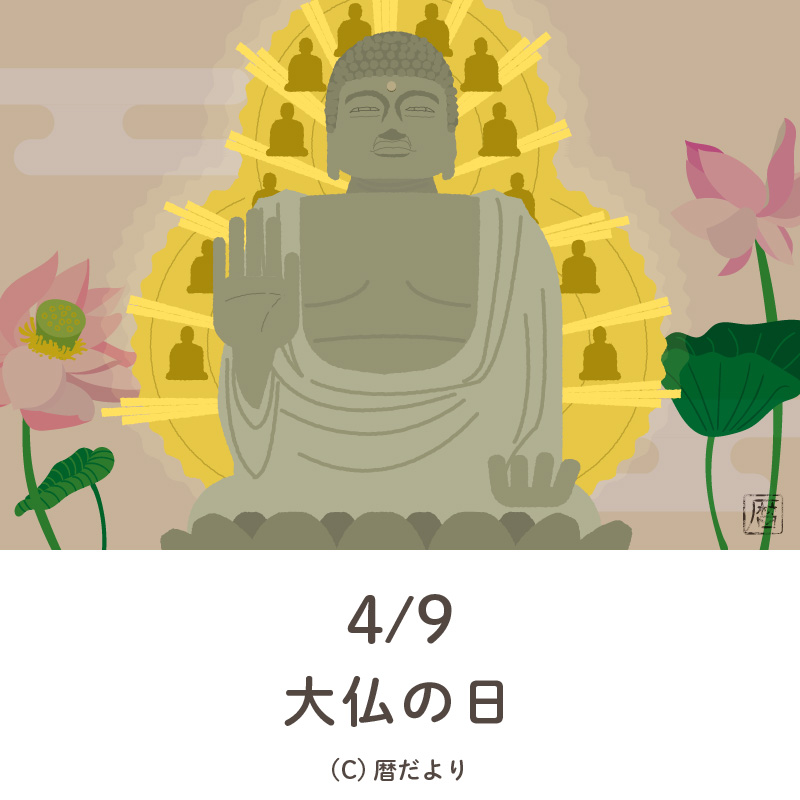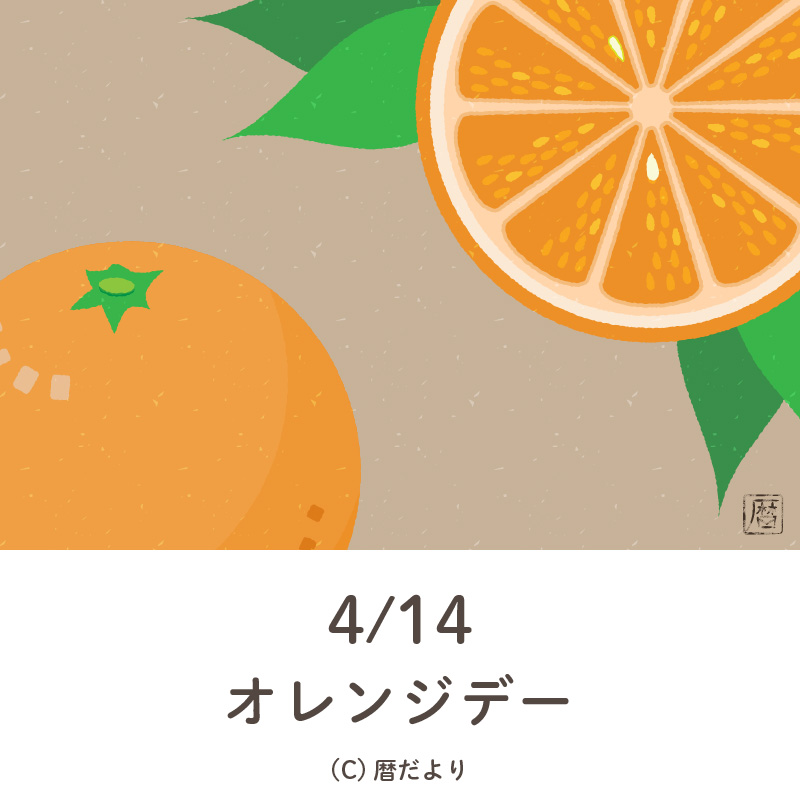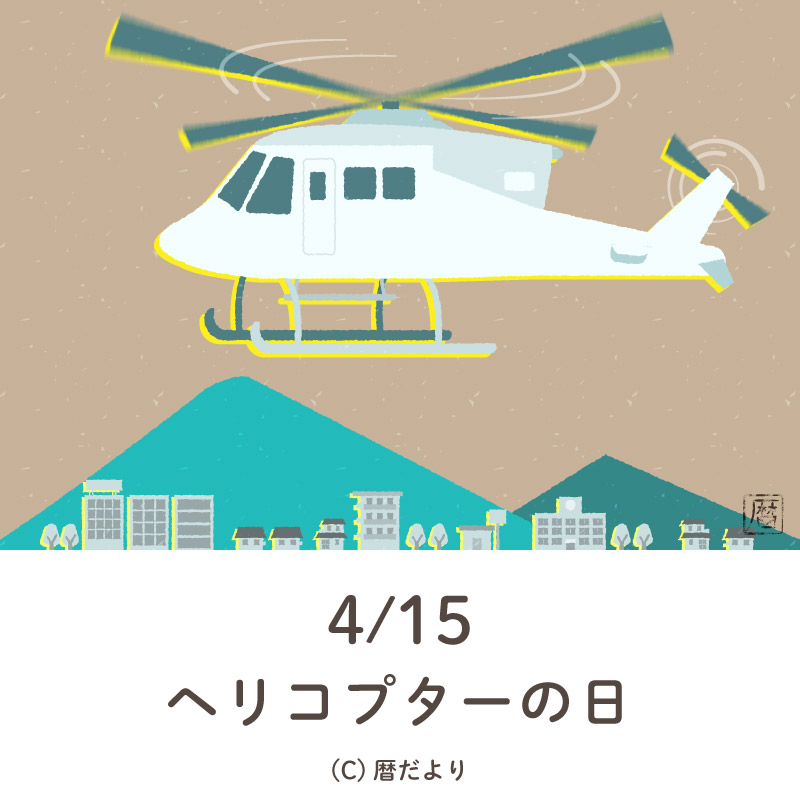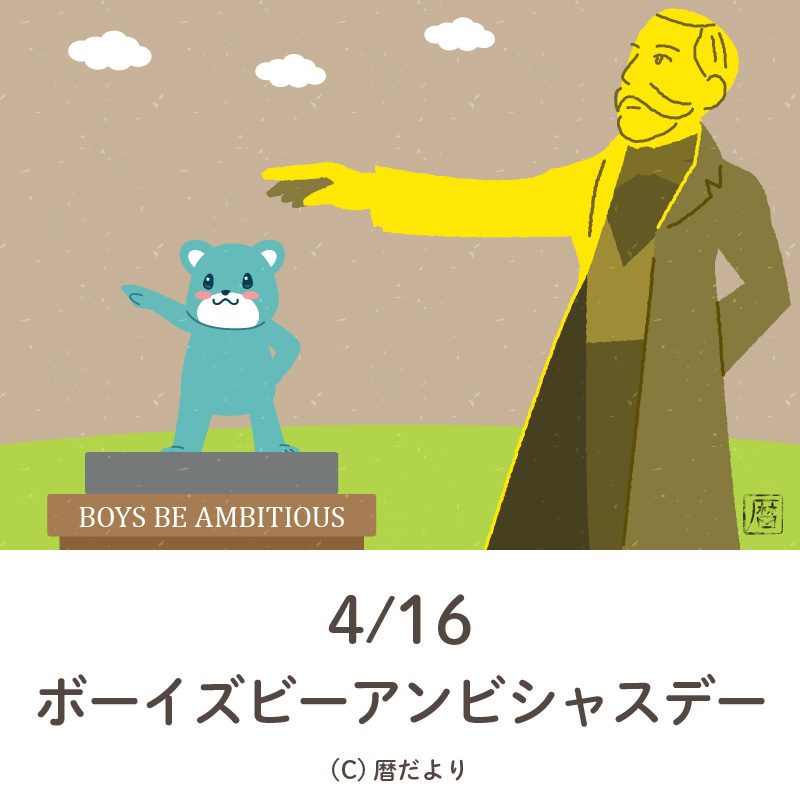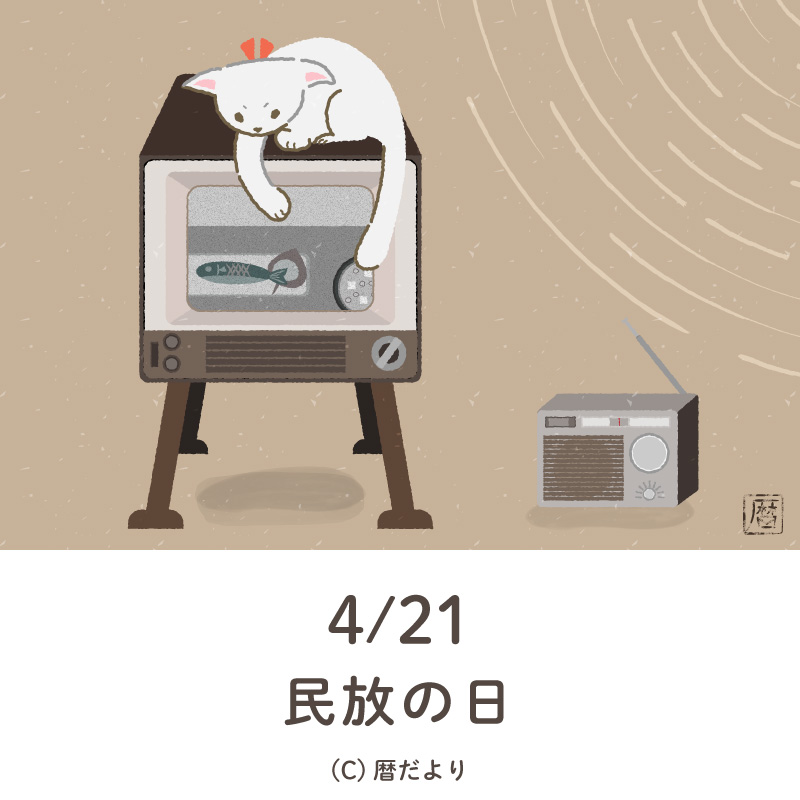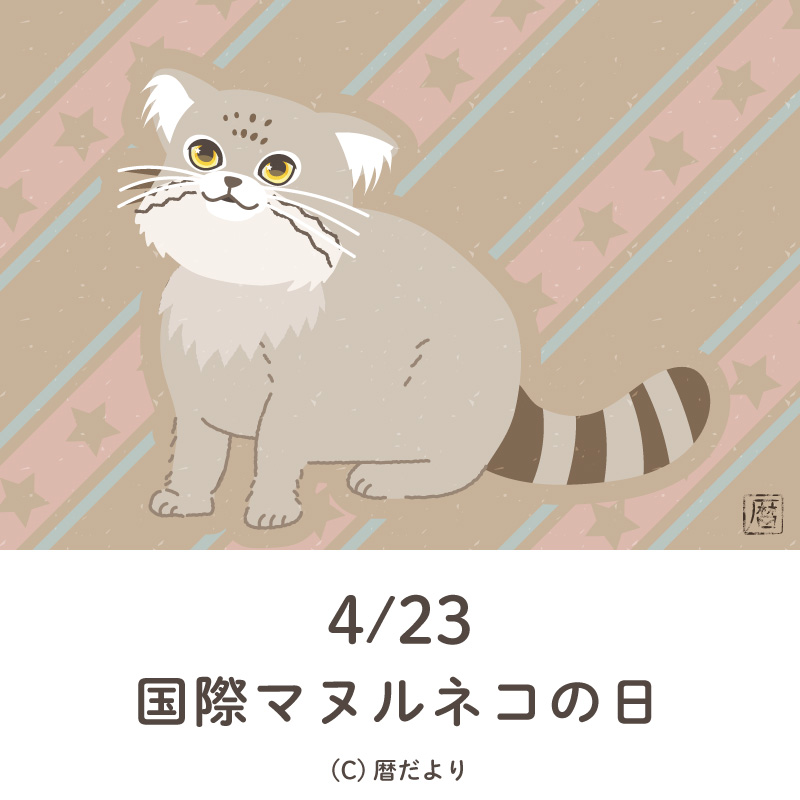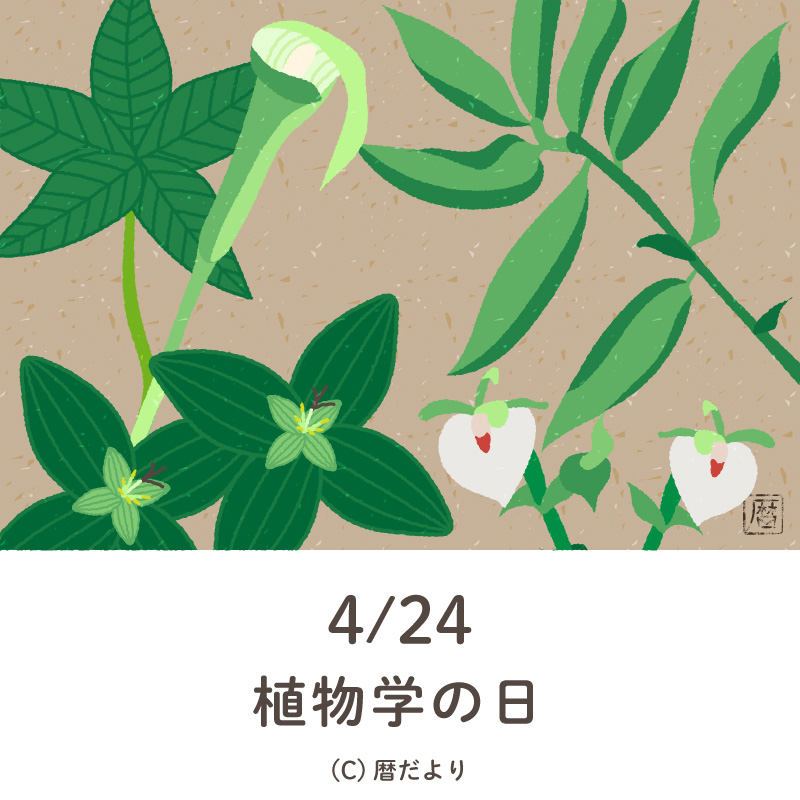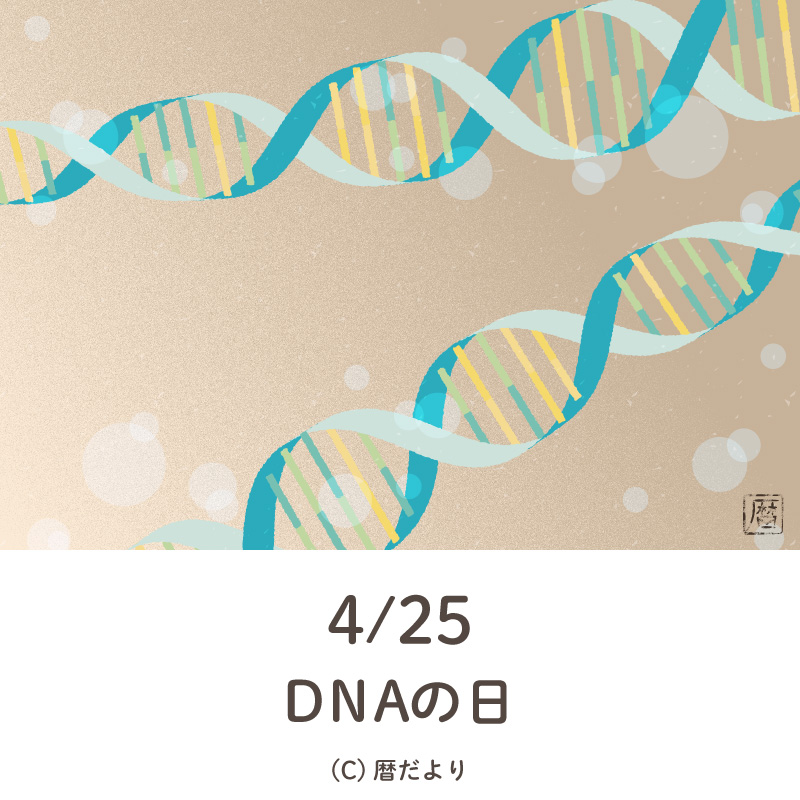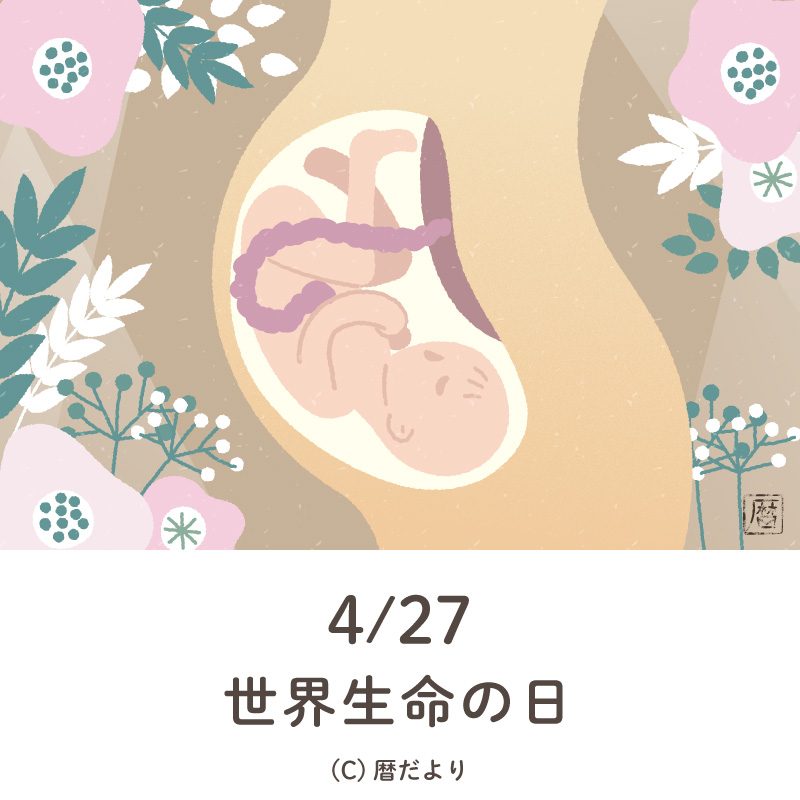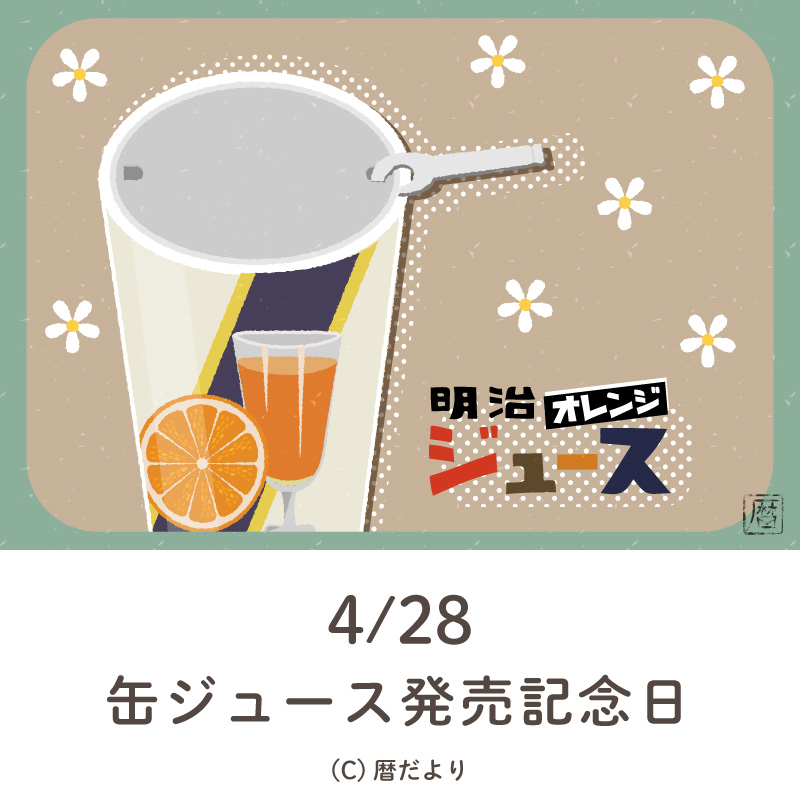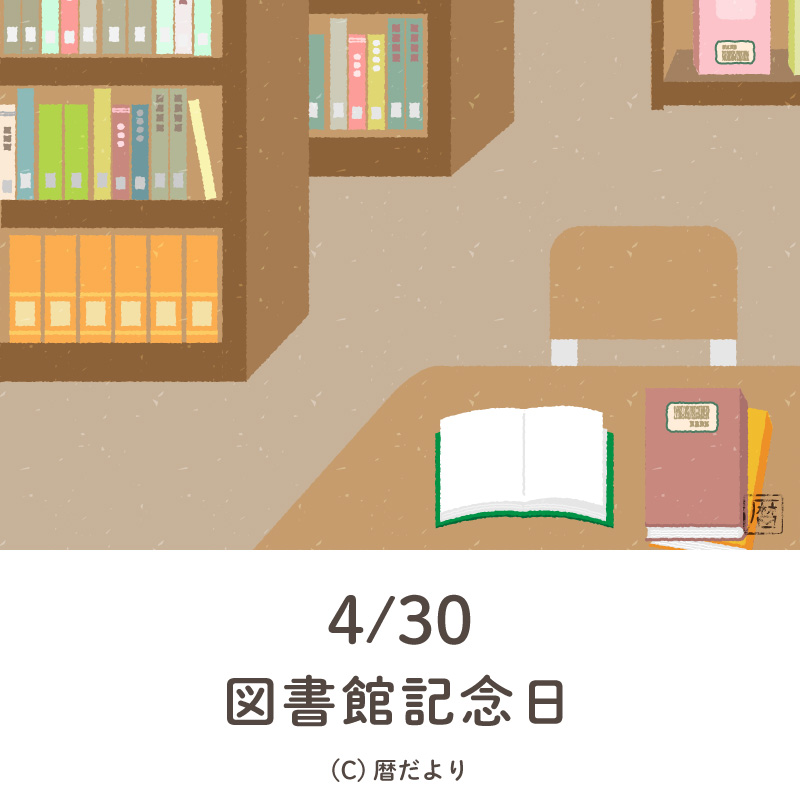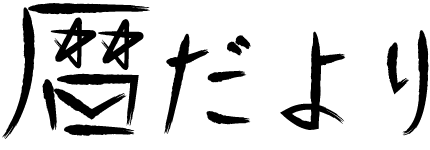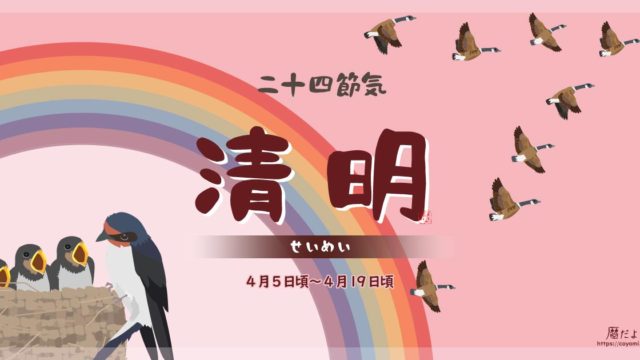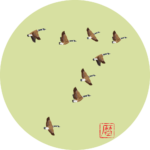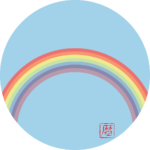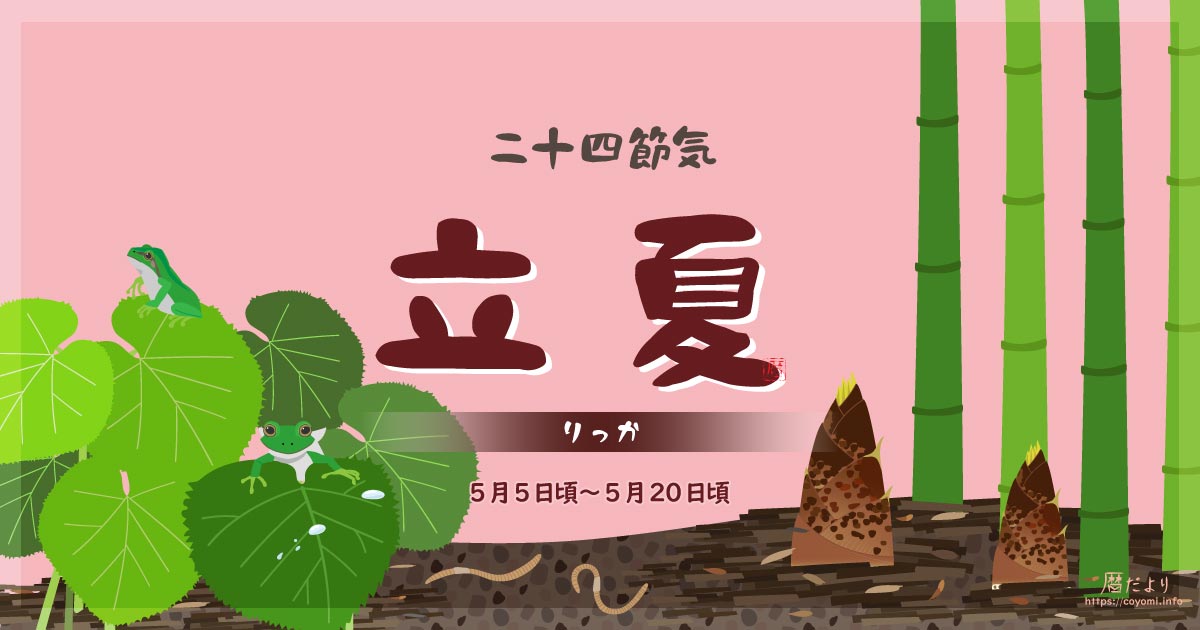四月の異名(和風月名)
ウツギの花が咲く季節という意味の「卯花月(うのはなづき)」を略したという説のほか、稲の苗を植える月という「苗植月(なえうえづき)」が転じたという説や、十二支でいうと四番目の「卯」にあたるからなど由来には諸説あります。
- 卯月(うづき)
- 種月(うづき)
- 植月(うえつき)
- 田植苗月(たうなえづき)
- 苗植月(なえうえづき)
- 夏初月(なつはづき)
- 陰月(いんげつ)
- 建巳月(けんしげつ)
- 鎮月(ちんげつ)
- 花残月(はなのこりづき)
- 卯花月(うのはなづき)
- 木葉採月(このはとりづき)
- 麦秋(ばくしゅう)
- 乾月(けんげつ)
- 孟夏(もうか)
- 正陽月(せいようげつ)
- 清和月(せいわづき)
- 得鳥羽月(えとりはのつき/とことばのつき)
- 夏端月(なつはづき)
- 余月(よげつ)
四月の節気
二十四節気
清明
【4月5日頃~4月19日頃】春の明るい陽光をうけ、万物が清々しくいきいきとしてくる頃
穀雨
【4月20日頃~5月4日頃】穀物を成長させる、春の優しい雨が降る頃
雑節
春の土用入り
立春の前18日間
春の土用は、4月16日頃から立夏の前日である5月4日頃までの約18日間。
「土用丑の日」といえば、「暑い頃に鰻を食べる日」として広く知られています。歳時記にも夏の季語として紹介され、土用は「夏」を連想しがちですが、実は年に四回、春夏秋冬それぞれに土用があります。
土用は「陰陽五行説」に由来します。古代中国では万物が木、火、土、金、水の五行の消長によって生成すると説かれました。自然界のものを5つの要素に分けるのは科学的な発想ですが、これを人間の運命などといった精神的なものや、四季のような「5」という数に分割できないようなものにまでに当てはめて解釈しようとしました。
季節をそれぞれ「春(木の芽が出る)→木、夏(烈火のごとく暑い)→火、秋(金属のように冷え冷えする)→金、冬(氷や雪に閉ざされる)→水」と割り当てたときに、「土」に当てる季節がないため、各季節の最後の18日前後を「土」としたのです。
季節の始まりは四立(立春、立夏、立秋、立冬)とされるので、この前日までの約18日間が土用ということになります。天保暦(旧暦)の暦法においては、太陽黄経が四立の18°手前になったとき、つまり27°、117°、207°、297°を土用の入りとしました。
土用はそれぞれの季節の終わりにあてられているため、次の季節への準備期間とされます。「土用の丑の日に鰻を食べる」という風習は、江戸の異才といわれた蘭学者の平賀源内によって仕掛けられたものだといわれています。うなぎ屋から商売繁盛を頼まれた源内は、土用の丑の日には「う」のつく食べ物を食べると良いという伝承から、うなぎ屋に「本日土用丑の日」という看板を立てたそうです。これが大ヒットし、夏バテ防止や体力増強のための対策として現在も続く習慣となっています。
ちなみに夏の土用には「丑の日」に「う」のつく食べ物ですが、春の土用には「戌の日」に「い」のつく食べ物、秋の土用は「辰の日」に「た」のつく食べ物、冬の土用は「未の日」に「ひ」のつく食べ物を食べると良いとされていました。また土用にちなんだ食べ物には、土用餅、土用蜆、土用鶏卵があり、特に土用餅は一年の厄を祓うとされました。これらは食べることで養生するというならわしです。
土用の晴れた日に、梅を干したり、衣類や書物を風通しして虫干しすることを「土用干し」といいます。
また土用の期間は「土気」が司るとされ、造作、修造、柱立、礎を置く、井戸掘り、壁塗りなど土を動かすことが凶とされました。特に秋は「土公が井戸に在り」といわれ、井戸堀りや井戸替えができませんでした。しかし旧暦時代において井戸は生活上必須のものだったため、土が動かせないのは生活上とても困るので「土用の間日」として井戸替えなどが出来る日が設けられています。
四月の行事と暮らし
行事・暮らし
エイプリルフール
4月1日
エイプリルフールは、嘘をついてもジョークとして許されるとされた日。
ヨーロッパでは18世紀頃に広まり、日本では大正時代になって広まったといわれています。またエイプリルフールのことを「四月馬鹿」や「不義理の日」ともいいます。
「四月馬鹿」とは、エイプリルフールの訳語ですが、4月1日の嘘に騙された人のことをさすこともあります。また「不義理の日」とは、中国の「万愚節」が江戸時代の日本に伝わったもので、元は、日ごろご無沙汰をしている人に、手紙などでわびる日だったそうです。
エイプリルフールの由来は世界各地に諸説ありますが、いずれも春の到来を祝う祭りが原型になっているとされています。
日本では「嘘」という言葉を使いますが、英語ではジョーク(冗談)やトリック(いたずら)、プランク(悪ふざけ)という単語で表現されることが多く、ライ(嘘)という言葉はあまり使われないようです。
花祭り(灌仏会)
4月8日
花祭り(灌仏会)は、仏教の開祖である釈迦の誕生日。
4月8日は仏教の開祖である釈迦の誕生日です。「花祭り」や「灌仏会(または仏生会)」などと呼ばれる「釈迦の誕生を祝う行事」が行われます。
山の花で飾った「花御堂」という小さな御堂を設け、その中央に安置された釈迦の像に甘茶をかけてお祝いをします。花御堂は釈迦生誕の地であるルンビニーの花園になぞらえらえたものです。
この灌仏会で祀られるのは「誕生仏」とも呼ばれるものです。釈迦は生まれてすぐに七歩歩き、右手で天を、左手で地を指して「天上天下唯我独尊」と唱えたといわれていますが、その逸話をかたどった仏像です。
誕生仏に甘茶をかけるのは、釈迦が生まれたときに九龍(九匹の龍)が天から降りてきて、香水といわれる清浄な水を注ぎ清めたという故事によるもので、釈迦の産湯の役目をしているといわれています。
灌仏会の甘茶は霊水とみなされ、拝んだ後に竹筒に入れて持ち帰り、家族で飲んで健康を祈願したり、家の周囲にまいて魔除けとしたり、甘茶で墨をすって虫除けのおまじない(「千早振る卯月八日は吉日よ、神さげ虫を成敗する」という歌)を書き、門口や戸に逆さまに貼ったりすることもあったようです。
卯月八日
4月8日
卯月八日は、各地で執り行われた豊穣祈願や先祖供養など各種の民間行事の総称。
灌仏会とは別に、農村部では4月8日に作物の豊かな実りを祈願する「卯月八日」という農耕儀礼が各地で行われていました。
卯月八日の習わしは地域によってさまざまですが、農事に先立って山に入り、飲食したり花摘みをしていました。
石楠花や山つつじ、樒、卯の花、山吹、空木などの花を摘んできて束にし、長い竹竿の先に取り付けて庭先に高く掲げる風習もあります。これは「天道花」と呼ばれ、神の籠る山から豊かな実りを感じる花を持ち帰ることで、田の神様が降りてくるための依り代とする意味がありました。
地域によって「高花」「夏花」など色々な呼び方があり、お天道様、お月様、お釈迦様など供える対象もさまざまですが、いずれも豊作と無病息災を祈願するものです。
卯月八日を山の神の祭日や山開きにあてているところが多く、「花折り始め」や「八日日の墓参り」として先祖を参ったり、「花見八日」「山慰み」「お山始め」など山から田の神を迎える儀礼をおこなう風習が各地でみられます。
十三詣り
旧暦3月13日(新暦4月13日)
十三詣りは、数え年で13歳になる子どもが、厄を払い知恵と福徳を授けてもらうために、虚空蔵菩薩に参拝する行事。
知恵詣りともいわれ、数え年で13歳になる子どもが旧暦の3月13日(新暦では4月13日)に虚空蔵菩薩に参拝する行事です。
虚空蔵菩薩は宇宙のように広大な慈悲と知恵をもった菩薩とされ、厄難を祓い、知恵を授けてもらうのが目的です。
数え歳の13歳は干支が一巡して自分の干支が回ってくる初めての年にあたります。
13という数字は、キリスト教では嫌われていますが、仏教では「死後13人の仏様が浄土へ導いてくださる」というありがたい数字であり、その13人目の仏様が虚空蔵菩薩とされています。
この虚空蔵菩薩の縁日(13日)と結びついて、十三詣りの風習が生まれたといわれています。
また女の子の13歳は、一人前になる年齢とみなされていたため、大人の着物(本裁ち)を着せて大人になることを祝った行事でもありました。参拝する前は着物の肩を縫い上げて「肩上げ」(袖の長さを調整する子どもの証とされた)をし、参拝が済んだら、この肩上げを取ってもらいました。
好きな漢字を一文字書いて奉納したり、境内で売られている13品の菓子を買ってお供えするところもあります。
祝日・記念日
国民の祝日
昭和の日
4月29日
「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」という趣旨の国民の祝日。昭和天皇の誕生日。
2006年(平成18年)までは「みどりの日」とされていましたが、2007年1月1日施行の改正祝日法により「昭和の日」として新設されました。「みどりの日」は、国民の休日とされていた5月4日に上書きするかたちで移設されています。
今日は何の日