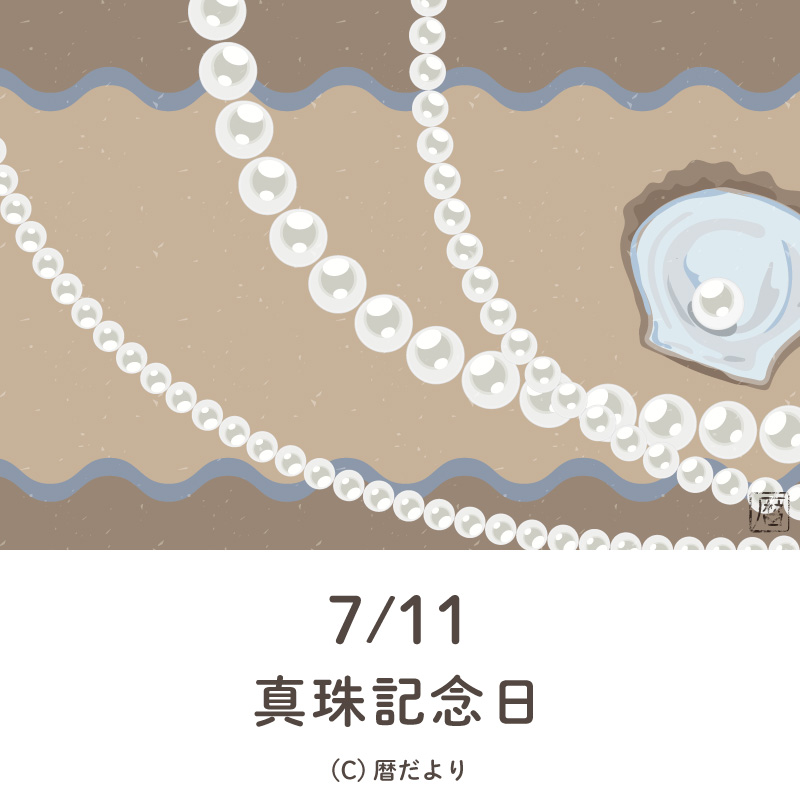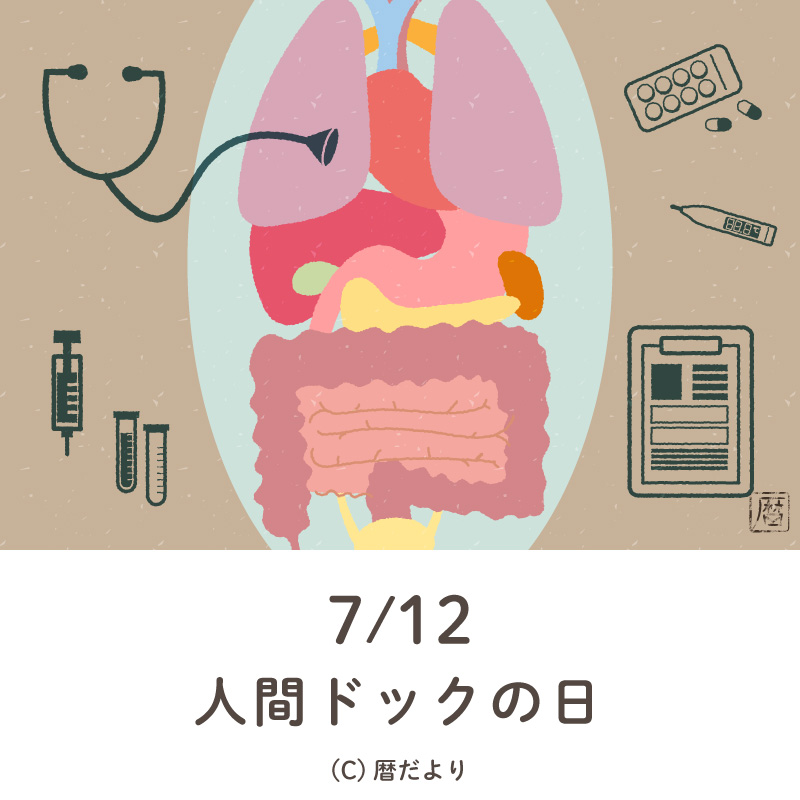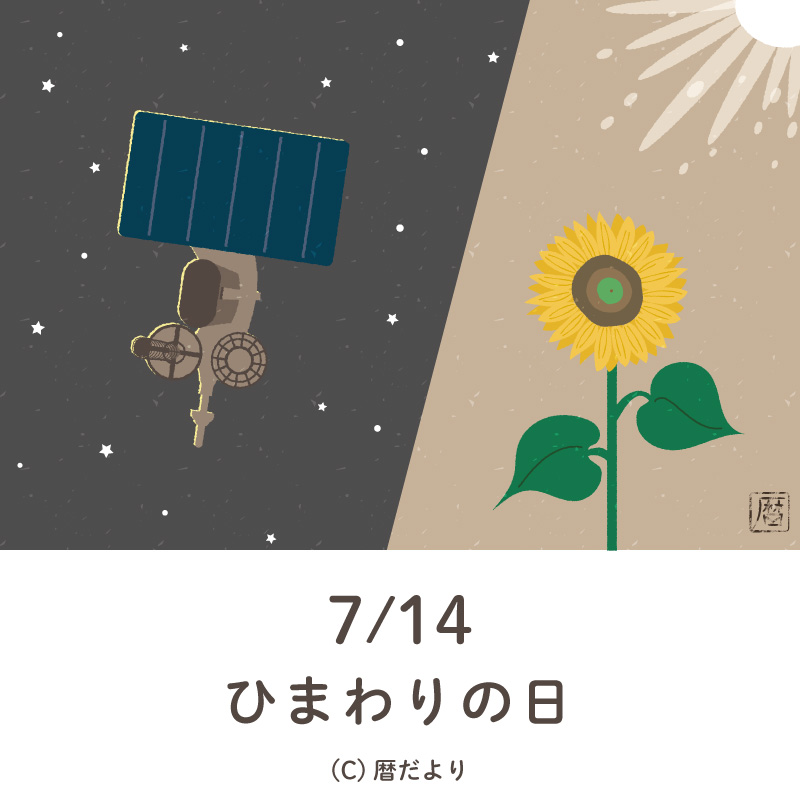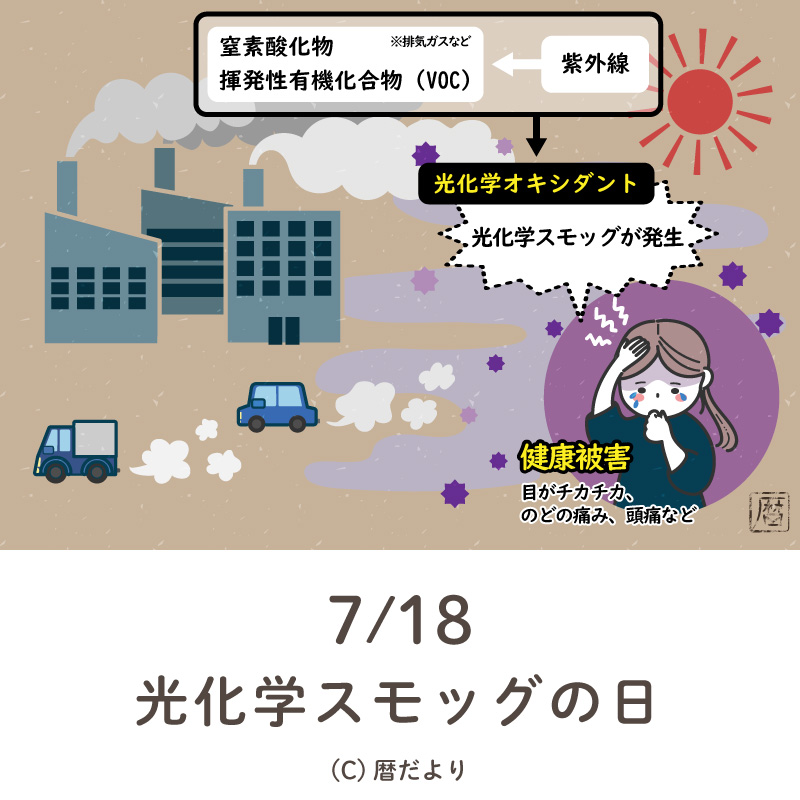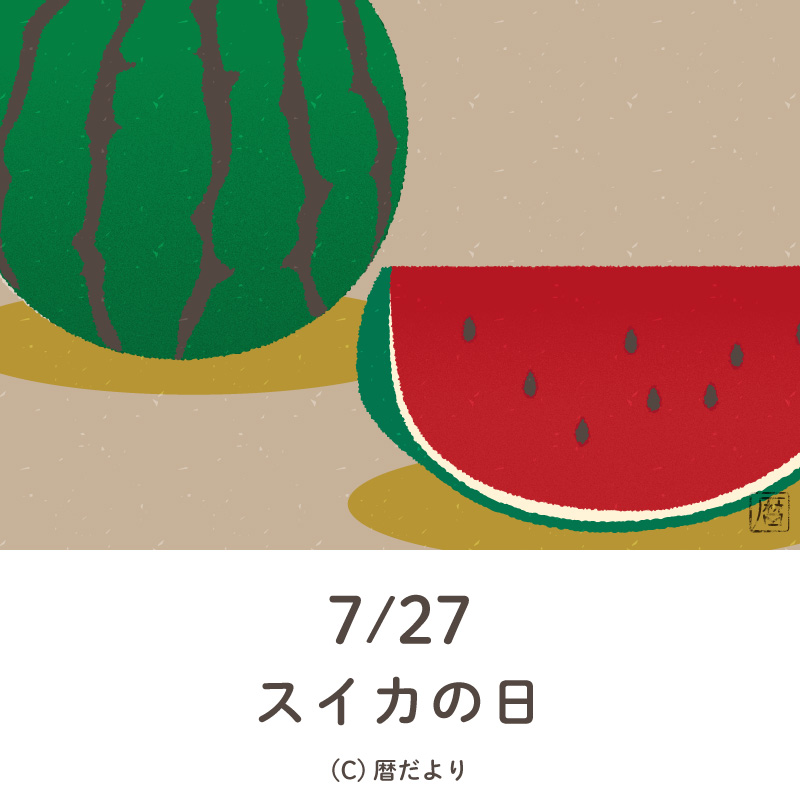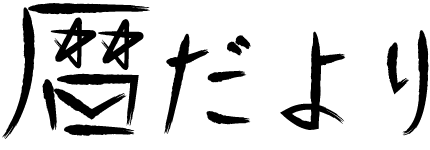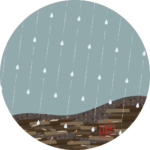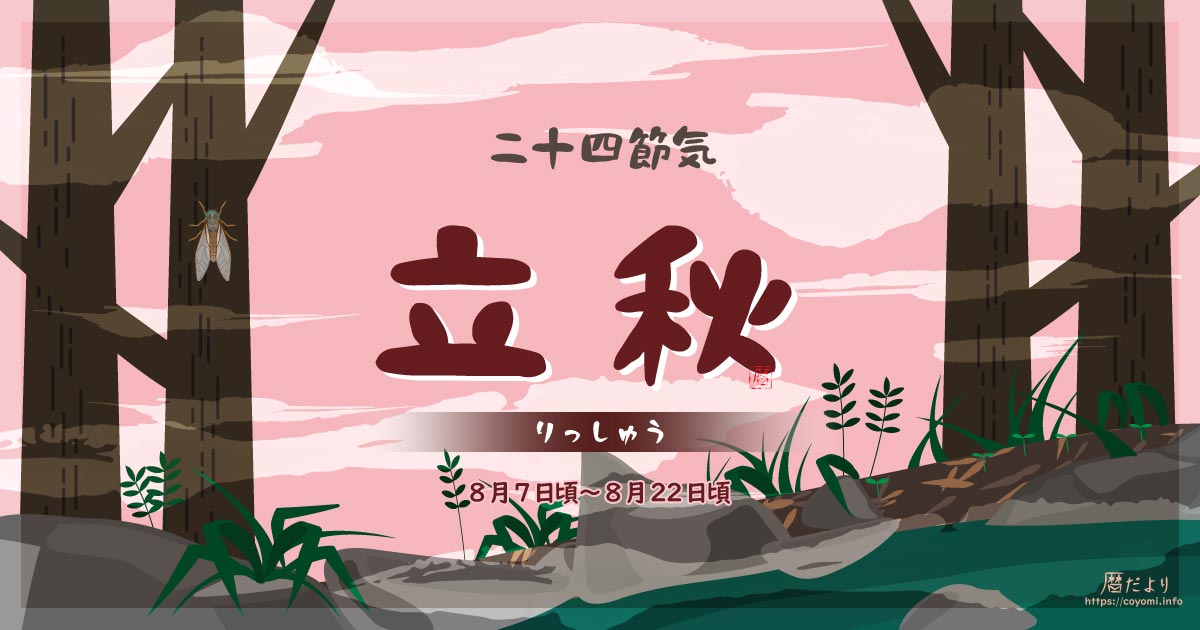七月の異名(和風月名)
七夕に詩歌を供える月、また書物をひらいて干す月「文披月(ふみひろげづき)」が略されたという説や、稲の穂が実る頃という意味の「穂含月(ほふみづき)」が転じたという説などがあります。
- 文月(ふづき、ふみづき)
- 七夕月(たなばたづき)
- 棚機月(たなばたづき)
- 女郎花月(おみなえしづき)
- 桐月(とうげつ)
- 愛逢月(めであいづき)
- 袖合月(そであいづき)
- 七夜月(ななよづき)
- 親月(しんげつ)
- 蘭月(らんげつ)
- 建申月(けんしんげつ)
- 初秋月(はつあきづき)
- 秋初月(あきはづき)
- 涼月(りょうげつ)
- 穂含月(ほふみづき)
- 穂見月(ほほみづき)
- 桐秋(とうしゅう)
- 含月(ふふみづき)
七月の節気
二十四節気
小暑
【7月7日頃~7月22日頃】梅雨が終わりを迎え、強い日差しに気温が上昇して暑い夏が訪れる頃。
大暑
【7月23日頃~8月6日頃】真夏の太陽が照り付け、うだるような暑さが続く頃。
五節句
七夕の節句
7月7日
七夕は、7月7日に笹飾りとお供え物をして夜空の星に祈りを捧げる星祭りの行事。
七夕は、古代中国から伝わった「牽牛星」と「織女星」の星伝説「七夕」と、裁縫や書道の上達を願う「乞巧奠」という風習、さらに日本独自の「棚機女」の伝説が結びついてうまれた行事で、宮中で行われたのが始まりだそうです。
「七夕」を「シチセキ」から「タナバタ」と読むようになったのは、この棚機女に由来するといわれています。
【中国「七夕」】
天帝の娘である織女と牛飼いの牽牛(日本では織姫と彦星)の夫婦が、仲が良すぎて仕事をしなくなり、それに怒った天帝が二人を天の川で隔てて別居させ、年に一度だけ会うことを許したという中国の星伝説。
織女星はこと座一等星の「ベガ」、牽牛星はわし座一等星「アルタイル」のことで、西洋でも一対の星とされる。天の川を飛ぶはくちょう座の一等星「デネブ」と結んで「夏の大三角形」。
【中国「乞巧奠」】
織女と牽牛の願いが叶う日ということにあやかって、裁縫や書道の上達を願う行事。
織女はもともと機織りを司る手芸の神とされ、織女星が天上にのぼる7月7日にお供えをして歌を詠んだ短冊などを飾り手芸の上達を願った。
【日本「棚機女」】
古事記に記されている古い神話に登場する乙女で、水神を迎えるために水辺に張り出した棚の上で美しい神衣を織る。
日本では古来より、機織りをして織り上がった布を先祖の霊に捧げて祀る行事があった。
また日本では七夕とお盆の関連も深く、先祖の霊を迎える前の禊の行事という意味もあります。七夕の日に子供や牛馬に水浴びをさせる「ねむた流し」や、七夕の翌日に祭りに使った笹や供物を川や海に流す「七夕送り」という風習がありますが、いずれもお盆前に身を清めるために行われます。
中国の星伝説「七夕」では、雨が降ると織姫と牽牛が会えなくなってしまいますが、日本では禊の行事とされていたため雨が降るほど良いとされることもあります。
また新暦の7月7日は梅雨が明けていない地域がほとんどで天の川がはっきり見えないことから、一ヶ月遅れて8月7日に七夕をおこなう地域もあります。
雑節
半夏生
夏至から数えて11日目
半夏生は、夏至から数えて11日目の7月2日頃。現在は太陽が黄経100度を通過する日。
半夏とは「カラスビシャク(烏柄杓)」という薬草のことで、この植物が生える頃ということから「半夏生」という言葉ができたといわれています。
半夏生は「気候の変わり目」として意識され、特に農家にとっては田植えを終える重要な目安でした。「半夏のあとに農なし」や「半夏半作」という言葉がありますが、この半夏生までに田植えを終えることができなければ、実りが遅れて半分しか収穫が見込めないとされていました。
また、地域によっては「半夏生に採った野菜を食べてはいけない」という言い伝えがあったり、「タコの足のように稲が八方に根を張るように」という願いを込めてタコを食べたりします。
夏の土用入り
立夏の前18日間
夏の土用は、7月20日頃から立秋の前日8月6日頃までの約18日間。本来、土用は一年に四回あるが、現在は夏の土用だけを指すようになっている。
雑節では立春、立夏、立秋、立冬の前18日間が土用とされています。季節の変わり目を無事に過ごすため、様々な禁忌を設けて戒めとしたり、次の季節へ移るための準備期間としました。
現在でも、夏の土用は有名です。「土用の丑の日に鰻を食べる」という風習は、江戸の異才といわれた蘭学者の平賀源内によって仕掛けられたものだといわれています。うなぎ屋から商売繁盛を頼まれた源内は、土用の丑の日には「う」のつく食べ物を食べると良いという伝承から、うなぎ屋に「本日土用丑の日」という看板を立てたそうです。これが大ヒットし、今日まで続く習慣となっています。
また土用の期間は「土気」が司るとされ、造作、修造、柱立、礎を置く、井戸掘り、壁塗りなど土を動かすことが凶とされました。特に秋は「土公が井戸に在り」といわれ、井戸堀りや井戸替えができませんでした。しかし旧暦時代において井戸は生活上必須のものだったため、土が動かせないのは生活上とても困るので「土用の間日」として井戸替えなどが出来る日が設けられています。
七月の行事と暮らし
行事・暮らし
山開き
7月1日
霊峰富士の山開き(その年はじめて登山が許可される日)。海水浴や川遊びの解禁も同時期。
日本の登山は山岳信仰と深く結びついています。
昔から山は神の籠る神聖な場所として崇められ、僧侶などを除いて入山は禁止されていました。しかし後に修験者が山岳修行の霊験を説くようになると、一般人も霊験を得ようと、夏期の一定期間だけ山頂に登り山岳の神との交流をするようになります。
つまり山開きとは、その年はじめて登山が許可される日ということです。
霊峰富士山では、白装束をまとい金剛杖を持った行者たちが「六根清浄」と唱えながら山頂を目指します。六根清浄とは「体の器官(六根)を清らかにし、心を無にして自然と一体化する」という意味が込められた、巡礼の際に唱える言葉です。
「六根清浄」がのちに「六根清」となり、転じて「どっこいしょ」となったともいわれています。
海開き・川開き
7月1日前後に、海水浴が解禁されることを「海開き」といいます。
また川遊びの解禁を「川開き」といい、江戸時代から行われている両国の川開きが有名です。隅田川では旧暦5月28日から8月28日までが納涼期間とされていました。一日目には花火が打ち上げられ、多くの屋形船や小舟が出て、川べりでは茶屋や寄席などの夜店が並んで賑わいました。通常夕方までの営業でしたが、川開きになると夜半までの営業が許可されたそうです。
四万六千日(ほおずき市)
7月10日
四万六千日は、一般には7月10日の観音菩薩の縁日。平日より多くの功徳が得られるとされる「功徳日」のひとつ。
四万六千日は、特定の縁日に参詣すると、平日より多くの功徳が得られるとされる「功徳日」のひとつです。この功徳日にお参りすると、一日で四万六千日分詣でたのと同じご利益があるといわれています。
一般には7月10日の観音菩薩の縁日をさしますが、寺で行われる縁日のひとつで「千日参り」や「千日詣」ともいわれます。
有名なのは東京・浅草寺で、観音堂の境内には「ほおずき市」が立ち、夏負けの厄除けとされる「ほおずき」が売られます。
江戸時代、ほおずきは遊びや薬用として人気のある植物でした。赤い実を揉んで種を抜き、水で洗ってから口に含んで鳴らして遊んだり、薬用としては青い実を陰干しにして鎮静剤にしたり、煎じて利尿剤や解熱鎮痛などに使われていました。
関西では月遅れの8月9、10日に観音様の縁日が行われます。これは「千日詣」といわれ、一日で千日分の功徳が得られるとされています。
お中元
7月1日から7月15日頃
お中元は、季節のあいさつを兼ねて、日頃お世話になっている方に感謝の気持ちを込めて品物を贈るしきたり。
お中元といえば、年末のお歳暮と同じく、季節のあいさつを兼ねて、日頃お世話になっている方に感謝の気持ちを込めて品物を贈るしきたりのことです。
もともとは古代中国の道教にある「三元節」に由来しています。中国では旧暦1月15日を「上元」、7月15日を「中元」、10月15日を「下元」とし、季節の変わり目に神に供物を捧げてお祝いをする習慣がありました。なかでも「中元」は、罪を懺悔し許す日として、終日庭で火を焚いて神を祀り、贖罪の意味を込めて近所の人に品物を贈ったそうです。
この習わしが江戸時代の日本に伝わり、お盆行事と時期的にも重なることから、お中元に品物を贈る習慣が定着しました。
お中元を贈る時期は7月1日から15日頃とするのが一般的で、これを過ぎると「暑中見舞い」、立秋(8月7日頃)以降は「残暑見舞い」として贈ります。
暑中見舞い
7月7日から8月7日頃
暑い盛りに相手の安否を気遣い、近況報告を添えたハガキを郵送するのが一般的。立秋(8月7日頃)を過ぎると「残暑見舞い」になる。
本来は、お中元の品物を携えて直接あいさつにうかがうのが暑中見舞いの作法とされますが、暑い盛りに相手の安否を気遣い、近況報告を添えたハガキを郵送するのが一般的です。
暑中見舞いを出す時期は、小暑(7月7日頃)から大暑(7月22日頃)を挟んで、立秋(8月7日頃)までとされています。小暑のころは梅雨の最中なので、梅雨明けする大暑ごろからが季節感にそうとされます。立秋を過ぎると「残暑見舞い」として出します。
祇園祭(夏祭り)
7月1日から一ヶ月間
祇園祭は平安時代から1100年以上続く伝統的な夏祭り。夏祭りは7月から8月の間に各地で行われ、京都・八坂神社の「祇園祭」は日本三大祭りのひとつ。
7月から8月の間に、各地で行われるのが夏祭りです。春祭りや秋祭りは農事に直結した祭りであるのに対して、夏祭りは疫病など人に害をなす悪霊を鎮めるためにおこなわれます。そのため水で穢れを清める行事も多くみられます。
夏祭りで有名なのが、日本三大祭りでもある京都・八坂神社の「祇園祭」です。八坂神社と呼ばれるようになったのは明治維新の神仏分離の時からで、それまでは「祇園社」と呼ばれていました。そのため夏祭りは「祇園御霊会」や「祇園会」といわれていました。
祇園祭は平安時代から1100年以上続く伝統的な夏祭りで、7月1日から一か月間にわたって行われます。
平安前期に都に疫病が流行った際、疫病を退治する神「牛頭天王」に当時の国の数と同じ66本の鉾を立てて疫病退散を祈祷した御霊会が起源といわれています。先の尖った木の棒に神が憑くと考えられていたため、鉾に悪霊を依り憑かせて燃やして退治しようとするものです。
祇園祭の最大の見せ所である山鉾巡行では、鉾先に大長刀をつけた長刀鉾が先頭に立ちます。大きな車輪を付けた山車に、神の使いとされる稚児を乗せて、鉾に疫病神を吸い込むため市街地を練り歩きます。
ちなみに、山鉾巡行が行われる7日間は八幡神社の神様は不在となります。15日の宵宮祭を経て神輿に神々の神霊を移し、17日夕方から24日まで四条寺町の御旅所に滞在します。
盂蘭盆会
7月13日から15日
盂蘭盆会は、先祖の霊をお迎えして供養する行事で、一般的には「お盆」といわれる。現在では月遅れの八月に行うところが多い。
「お盆」は先祖の霊をお迎えして供養する行事で、正式には「盂蘭盆会」「精霊会」といいます。
お盆は、仏教の経典に書かれた説話が起源になっているといわれています。お釈迦様の弟子である目連が、神通力で母親が死後に餓鬼道に堕ちたことを知り、救う方法をお釈迦様に問うたところ「7月15日に僧たちにご馳走を供えて母親の回向を頼みなさい」と教えられたのが由来だそうです。
インドから中国を経て、「あの世で苦しんでいる死者を供養して救う」という仏教の風習が、飛鳥時代の日本に伝わりました。それが日本古来の「魂祭」という先祖を祀る行事と融合し、お盆の習慣が民間に普及していったと考えられています。
盆入りの13日に、家の前で稲わらなどを燃やして先祖の霊をお迎えすることを「迎え火」といいます。そして盆の終わる15日の夕方か盆明け16日朝に、迎え火と同じように火を焚いて先祖の霊を帰しますが、これを「送り火」といいます。この習慣は江戸時代ごろから盛んになったそうです。
先祖の霊が迷わず帰ってこれるようにと、軒先に提灯を下げたり、「キュウリの馬」と「ナスの牛」をつくって精霊棚に飾ったりします。これは先祖の霊を送り迎えするための乗り物とされています。
もともとは旧暦七月の行事ですが、現在では月遅れの八月に行うところが多くなっています。
祝日・記念日
国民の祝日
海の日
7月第3月曜日
「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」ことを趣旨とした国民の祝日。祝日化される前は「海の記念日」。
1995年(平成7年)に制定され、翌1996年(平成8年)から施行されました。制定当初は7月20日でしたが、2003年(平成15年)に改正された祝日法のハッピーマンデー制度により、7月の第3月曜日となりました。
海の日については「国民の間に広く海洋についての理解と関心を深めるような行事が実施されるよう努めなければならない」と法律で定めているため、海上自衛隊や国土交通省海事局が行事を開催しています。
今日は何の日