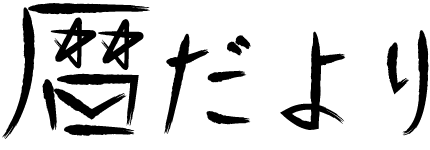春分(しゅんぶん)
- 3月21日頃
- 黄経0度
昼と夜の時間の長さがほぼ同じになる日。この昼と夜とは、明暗の時間の長さではなく日の出と日の入りを基準とする。
二十四節気において「二至二分」とされる重要な日。天保暦以降に取り入れられている定気法では、春分を基準(黄経0度)とし、地球から太陽の位置が15度移動するごとに一節気が進む。
春分を中日として、その前後3日をあわせた7日間が「春のお彼岸」で、先祖の供養や農作業事始めの神事がおこなわれる。
「暑さ寒さも彼岸まで」というように、寒さを脱して過ごしやすい気候となる頃。
春分の七十二候
初候:雀始巣
【時期】3月21日~25日頃
【読み】すずめはじめてすくう
【意味】雀(すずめ)が巣をつくり始める

雀は、二月頃につがいとなり、三月に巣作りを始めると言われています。
次候:桜始開
【時期】3月26日~30日頃
【読み】さくらはじめてひらく
【意味】桜が咲き始める

七十二候に桜が入っているのは日本独自のものです。
元々は、春分の次項が「雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす)」、末候が「始電(はじめていなびかりす)」でした。
日本の七十二候は、1684年の貞享改暦の際に「本朝七十二候(新制七十二候)」として、渋川春海により日本の実情に合わせてアレンジされています。
末候:雷乃発声
【時期】3月31日~4月4日頃
【読み】かみなりすなわちこえをはっす
【意味】雷が鳴り始める

春の雷は恵みの雨を呼ぶ兆しとして喜ばれていました。大気が不安定な頃で、強風が吹いたり、時には雪や雹を降らせることもあります。
「春の嵐」は、3月から5月頃にかけて、桜前線の北上と共にやってきます。北から入り込んでくる冷たい空気と、南から流れ込む暖かいがぶつかることで、温帯低気圧が急速に発達し、台風並みの猛威をふるいます。
台風と違うのは、短時間で急速に発達するので予測が難しいうえに、温帯低気圧の中心から離れた場所でも強い雨風が吹きやすく、広範囲に被害を及ぼすので注意が必要です。