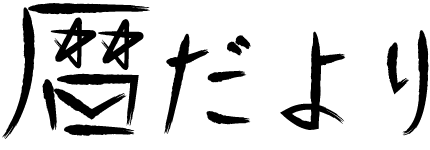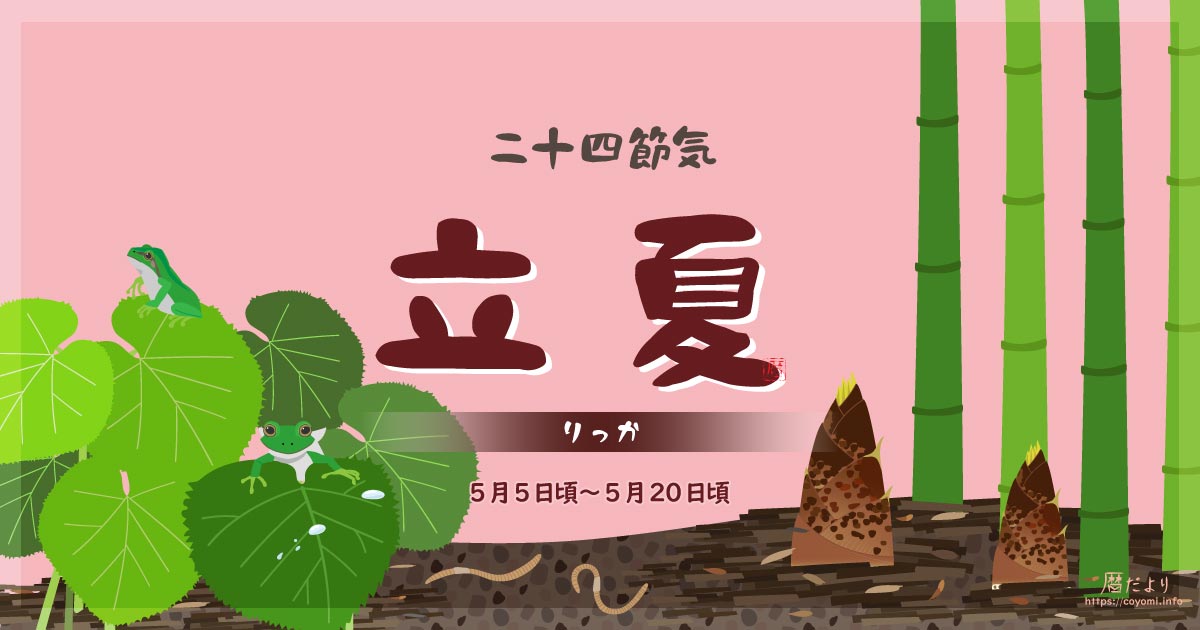小満(しょうまん)
- 5月21日頃
- 黄経60度
初夏の日差しを浴びて草木や生物がすくすく育ち、天地のあらゆる生命に力が満ちる頃。
小満とは「陽気が天地に満ちる」という意味の言葉。5月下旬にもなると気温も湿度も高くなり、少し動いただけで汗ばむ感じがする季節となる。梅雨を前に、麦の収穫や田植えの準備など農家にとっては活気あふれる忙しい時期。
ちなみに沖縄では小満から芒種にかけての時期に梅雨があたるため、梅雨のことを「小満芒種」「芒種雨」と呼ぶこともある。
「小満」とは、やや観念的で分かりにくい言葉なので、その意味については様々な説明がされている。
農作物の収穫が生活の糧となる農家にとって「作物(秋に蒔いた麦)の成長が確認でき、ひと安心できる時期」ということで、「少し満足する」という意味のある「小満」という名がついたという説や、二十四節気の作られた中国北方では、大麦や小麦など夏の作物が実って穂が膨らみ始める頃だが、まだ成熟はしていないため「小満」という名がつけられたともいわれている。
ちなみに大小のつく言葉は「大暑・小暑」「大寒・小寒」と対になっているが、小満はひとつだけで対はない。
小満の七十二候
初候:蚕起食桑
【時期】5月21日~25日頃
【読み】かいこおきてくわをはむ
【意味】蚕が桑の葉を盛んに食べ成長する

蚕は野生の蛾を数千年かけて家畜化したものです。蚕は生糸を効率的に多く採ることを目的として品種改良が重ねられました。
そのため幼虫はほとんど移動せず、成虫は羽があるのに飛べません。
蚕は貴重な絹糸をつくって人々の生活を支えていたため「お蚕さま」「お蚕さん」などと呼ばれ、虫のように「匹」ではなく、牛などの家畜と同じように「頭」で数えられました。
卵から孵化した長さ1ミリほどの稚蚕は、25日余りで60ミリ(体重でいうと約1万倍)にも成長します。そして白い糸(繭けんし糸)を体の周りに吐き出しながら自らを包む繭をつくり、中でサナギとなるのです。この繭が生糸になります。
養蚕は約5,000年前の中国で始まり、その後シルクロードを渡って、日本に伝わったのは江戸時代といわれています。全国に広がり、明治時代頃になると農家の約4割が養蚕に携わっていました。養蚕が最も盛んだった大正から昭和初期には、絹が日本の輸出の主力製品となり、「ジャパンシルク」として世界市場の6割を占めることもあったそうです。
「蚕時雨」という春の季語がありますが、蚕が桑の葉を食べ進める「シャワシャワ」「パラパラ」というような音が、サーッと静かに降る雨の音に似ていることからつくられた言葉です。しかし養蚕業では大量の蚕を飼育しているので、時雨というより猛烈な大雨が屋根を打つような音と言われることもあるようです。
また、陰暦4月の異名である「木葉採月」は、蚕の成長に欠かせない桑の葉を摘む頃という意味があります。桑の葉が収穫できる5月から10月までに3~4回蚕を育てますが、およそ3トン~4トンもの桑の葉が必要になることもあり、養蚕期はとにかく給餌作業が大変でした。現在では桑の葉ではなく人工肥料で飼育されているそうです。
ちなみに、ちょうど同じ時期に採れる野菜の「ソラマメ」は、さやの形が蚕の繭に似ていることから「蚕豆」とも書かれます。
次候:紅花栄
【時期】5月26日~30日頃
【読み】べにばなさかう
【意味】紅花が盛んに咲く

小満の次候「紅花栄」の紅花とは、一般にはアザミに似たキク科の花で、6月から7月の梅雨の時期に真黄色の花を咲かせる「ベニバナ」だといわれています。
ベニバナの原産はアフリカのエチオピアといわれ、古代エジプト時代から染料として利用されていました。
花からは染料が、種からは紅花油(サフラワーオイル)が、花を乾燥させると漢方薬ができます。
日本にはシルクロードを渡って飛鳥時代に伝わり、中国の呉の国から来た藍色という意味で「呉藍」(転じて「くれない」)と呼ばれたり、茎の先端につく花を摘み取って染色に用いることから「末摘花」などと呼ばれました。
ベニバナの栽培は近畿地方を中心に広がり、特に山形県の最上(現・村山)地域では、昼夜の寒暖差や肥沃な土壌など、その風土を活かして盛んに栽培されました。当時のベニバナは「米の100倍、金の10倍」といわれる高級品で、特に最上でつくられるベニバナは質が良く「最上紅花」と呼ばれて全国に知られ、山形地方の経済を支えていました。現在は山形県の県花に指定されています。
ベニバナは黄色の花ですが、受粉すると山吹色から少しずつ赤色に変わります。ベニバナの花弁には「黄色素サフロールイエロー」と「赤色素カルサミン」の2種類の色素が含まれており、これを取り出したものが染料や口紅の元として使用されました。黄色素は水溶性で容易に取り出せるので衣類を染めたり食べ物に着色するのに広く利用されましたが、赤色素は水に溶けないため「紅餅」(※紅花の花弁に水を加え、酸化させて餅状にしたものを、平たく伸ばし乾燥させて作ったもの)など、色素を取り出すための様々な技術が開発されました。赤色素はわずか1%ほどしか含まれていないため、紅花染の紅はとても高価なものでした。また紅花から作り出される赤い色は魔除けの色としても崇められてきました。
ところで、七十二候「紅花栄」というのは、江戸時代の暦学者・渋川晴海が日本の実情に合わせてアレンジした「本朝七十二候」から登場したものです。元は「靡草死」(※「田の畔に生える草などが暑さに枯れる」という意味)でした。
そのため、この「紅花」は、実はベニバナではないという説もあります。七十二候の「紅花栄」が「ベニバナ」である根拠は、「七十二候鳥獣虫魚草木略解」(1821年)に「紅花ハ紅藍花ナリ 和名鈔ニクレノアヰト云 今ハヘニハナト云」(※意訳:「紅花」とは「紅藍花」のことである。和名類聚抄には「くれのあい」とあり、今は「べにばな」という)と書かれているからとされています。しかし、ベニバナの開花時期は5月から7月で、見頃となるのは6月下旬~7月上旬です。
小満の頃に見頃となる赤い花といえば「サツキツツジ」です。渋川晴海が「本朝七十二候」を発表した江戸時代は、特にツツジの栽培や品種改良が盛んに行われていました。そのため、七十二候「紅花栄」の「紅花」は、実は「ベニバナ」ではなく、5月末頃に赤い花をたくさん咲かせる「サツキツツジ」を指していると考えたほうが納得できます。
末候:麦秋至
【時期】5月31日~6月5日頃
【読み】むぎのときいたる
【意味】麦の穂が黄金色に熟し収穫を迎える
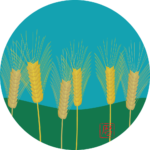
晩秋から初冬に蒔いた麦が収穫の時期を迎えます。「秋」は穀物や果物の収穫が多くなる季節です。そのため「秋」という言葉に「成熟した作物を収穫する時期」という意味を持たせたのが「麦秋」です。麦秋は、夏の季語でもあり、陰暦4月の異名にもなっています。
日本では、鎌倉時代から「二毛作」が普及し、米の裏作として大麦(六条大麦)が栽培されるようになりました。稲作が終わった田んぼに麦を播き、麦を収穫してから田植えが始まるのです。
「五穀豊穣」は「穀物が豊かに実ること」いう意味の言葉ですが、五穀とは人々が主食としていた穀物の総称で「米・麦・粟・豆・黍(一説には稗)」のことです。大麦は、かつては米の不足を補う重要な主食でした。白米に比べて食物繊維やカルシウム、カリウムなどが豊富で、糖質が少ないため、近年では健康食材として注目されています。
この時期に強く吹いて麦を揺らす風の事を「麦嵐」「麦風、麦の秋風」といい、風にそよぐ金色の穂を「麦の波」、その頃に降る雨を「麦雨」と呼びます。