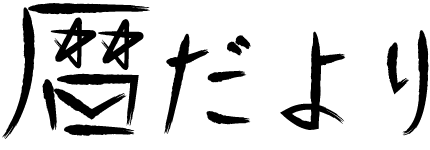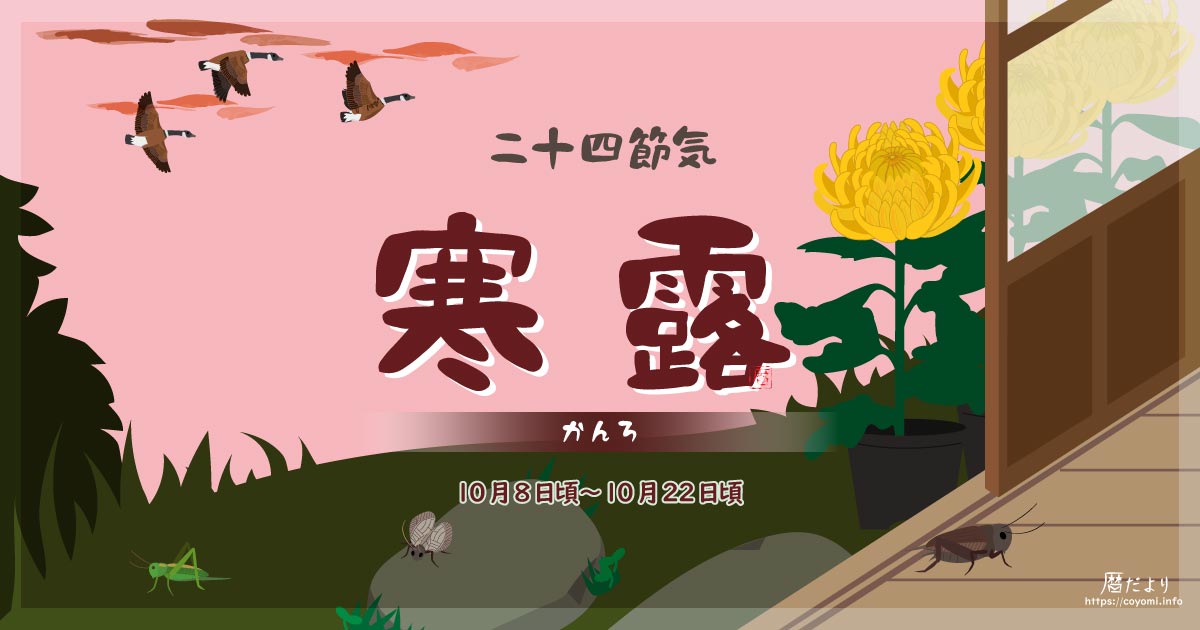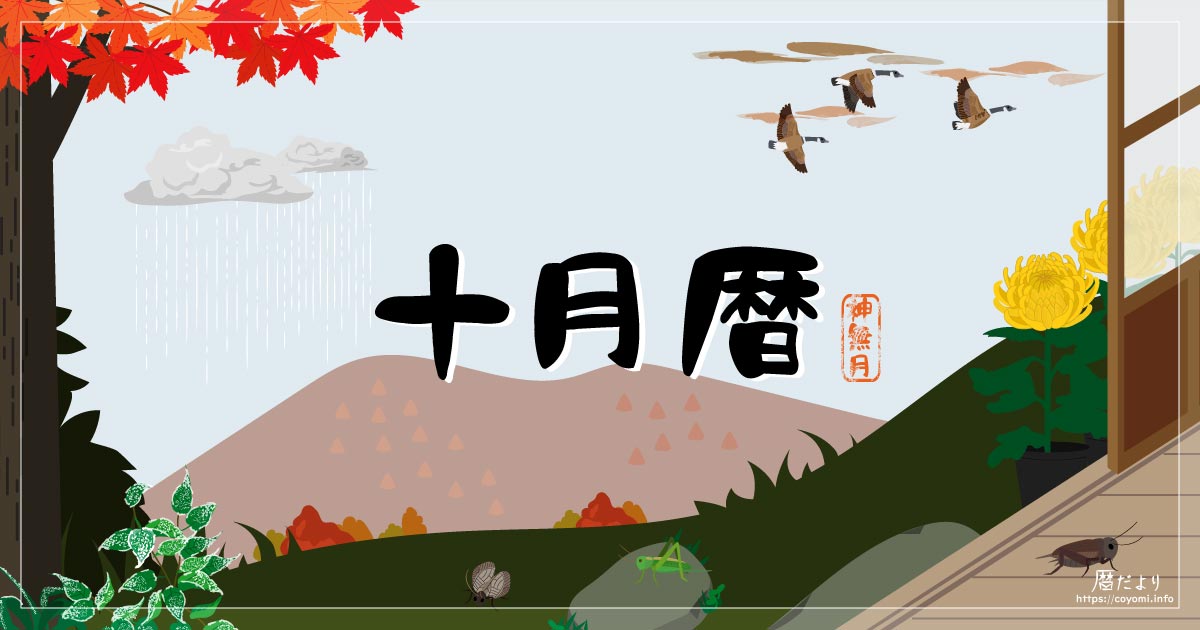霜降(そうこう)
- 10月23日頃
- 黄経210度
秋が深まり冷え込みが増してきて、北の里山では霜が降り始める頃。
気温が下がって紅葉は最盛期を迎え、北国や山間地では朝夕の露が白い霜へと変わっていく。この日から立冬までに吹く北風のことを「木枯らし」という。
また「小春日和」とは、晩秋から初冬(陰暦10月(新暦11月)頃)の暖かく穏やかな晴天のこと。春先の暖かい日と間違えられることも多いが、小春日和は冬の季語。
霜降の七十二候
初候:霜始降
【時期】10月23日~27日頃
【読み】しもはじめてふる
【意味】霜が初めて降りる

気温の低い夜間から早朝に、空気中の水蒸気が、地面や草の葉の表面に付着してできる氷の結晶のことを「霜」といいます。
むかしは、霜は雪と同じように空から降ってきたと思われていたため「降る」という言葉が使われています。
北の地域や標高の高い山間部では霜が降り始める頃ですが、平地では朝晩が冷え込む程度で霜を見ることはありません。
次候:霎時施
【時期】10月28日~11月1日頃
【読み】こさめときどきふる
【意味】時雨がときどき降る

秋の末から冬の初めごろ、さあっと降ってやむ通り雨や、しとしと静かに降る小雨のことを「時雨」といいます。時雨は元来「じう」という漢語で「ほどよいときに降る雨」という意味でした。
また、時雨が降る頃から気温がぐっと下がっていくので、人や動物に冬支度を促す合図だともいわれていました。
ショウガを加えた佃煮のことを「しぐれ煮(時雨煮)」といいます。しぐれ煮の発祥は三重県桑名市で、「桑名で獲れるハマグリを短時間でさっと煮てつくる様子」を「さっと降ってすぐにやむ時雨」に例えたという説や、「ハマグリの美味しい時期と時雨の季節が重なっていたから」という説。他にも、「食べると様々な風味が口の中を通り過ぎる」のを「通り雨のような時雨」に見立てたという説があります。
末候:楓蔦黄
【時期】11月2日~6日頃
【読み】もみじつたきばむ
【意味】モミジやツタが色づく

秋が深まるにつれて、平地でも紅葉が彩りを増していきます。
日本では万葉の時代から桜の季節に花見をするように、秋には紅葉を楽しんできました。
「紅葉」の語源は「揉みいず」で、「色が揉み出される」という意味があるそうです。他にも、草木が黄色や紅に染まることを「紅葉つ(黄葉) 」と言い、色付いた落ち葉のことを「もみち」と言っていたからという説もあります。