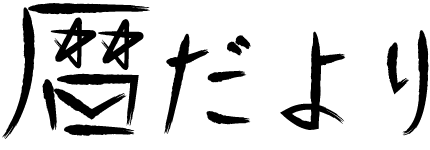清明(せいめい)
- 4月5日頃
- 黄経15度
春の明るい陽光をうけ、万物が清々しくいきいきとしてくる頃。
清明の前後は桜前線が北上するため、一年のうちもっとも華やかな季節となる。気温の上昇とともに成長し開花する桜も、農作業の目安のひとつとされた。
「清明」は「清浄名潔」の略で、晩春の季語となっている。
清明の七十二候
初候:玄鳥至
【時期】4月5日~9日頃
【読み】つばめきたる
【意味】ツバメが南から渡ってくる

9月~10月頃に日本を離れ、冬の間は暖かい東南アジア(台湾、フィリピン、マレー半島、インドネシア)のほうで過ごしていたツバメが、春になると海を渡って日本にやってきます。
距離にしておよそ2,000km~5,000km。太陽の位置を方角の目安にして飛ぶといわれ、その最高速度は時速200㎞にもなるそうです。
ツバメのように、繁殖地と越冬地が違う鳥のことを「渡り鳥」といいます。
このツバメの飛来とともに本格的な農耕が始まります。冬の間は姿を消し、春とともにやってくるツバメはとても神秘的で、農作物を食い荒らす害虫を食べてくれるので、富をもたらす縁起の良い鳥とされました。
次候:鴻雁北
【時期】4月10日~14日頃
【読み】こうがんかえる
【意味】雁が北へ帰っていく
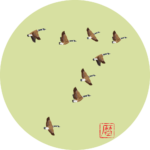
ツバメの飛来と反対に、冬鳥である雁がユーラシア大陸と北アメリカ大陸の北極圏へと帰っていきます。渡りの距離は約4,000㎞ともいわれます。
雁は、カモより大きく、ハクチョウよりも小さいカモ目カモ科の水鳥の総称です。
雁のような大きな渡り鳥はV字に編隊して飛びます。これは、前の鳥の羽ばたきによってうまれた上昇気流に乗ることで、後ろの鳥は飛ぶエネルギーを抑えることができるからです。先頭は疲れるので時々交代しているそうです。
二十四節気「寒露」(10月9日頃)の初候は、これと対になる「鴻雁来」となっています。
末候:虹始見
【時期】4月15日~19日頃
【読み】にじはじめてあらわる
【意味】虹があらわれ始める
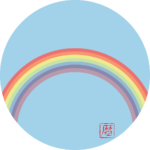
春が深まり空気が潤いはじめると、虹が見られるようになります。
虹は空気中の水滴に太陽の光が屈折や反射をして見える現象です。光は波長によって屈折率が異なるため「赤、橙、黄、緑、青、藍、紫」に分かれて見えるのです。
虹を七色と決めたのは、万有引力で有名なニュートンです。当時のヨーロッパでは、学問のひとつであった音楽と自然現象を結び付けることが重要だとされていたため「ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ」の七音に色を当てはめ、虹を「七色」としたそうです。ニュートンは「7」という数字を「宇宙において重要な意義を持つもの」だと考えていたため、虹の色数も「7」に対応させたという説もあります。
また、古代中国では「龍になる大蛇が天空を貫くときに空に作られるものが虹」と考えられていました。虫偏はもともとは龍を意味する象形文字で、これに貫くという意味の「工」を併せて「虹」という漢字になったそうです。