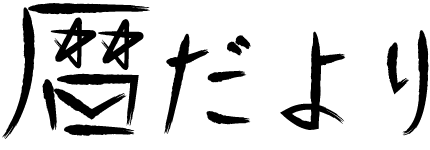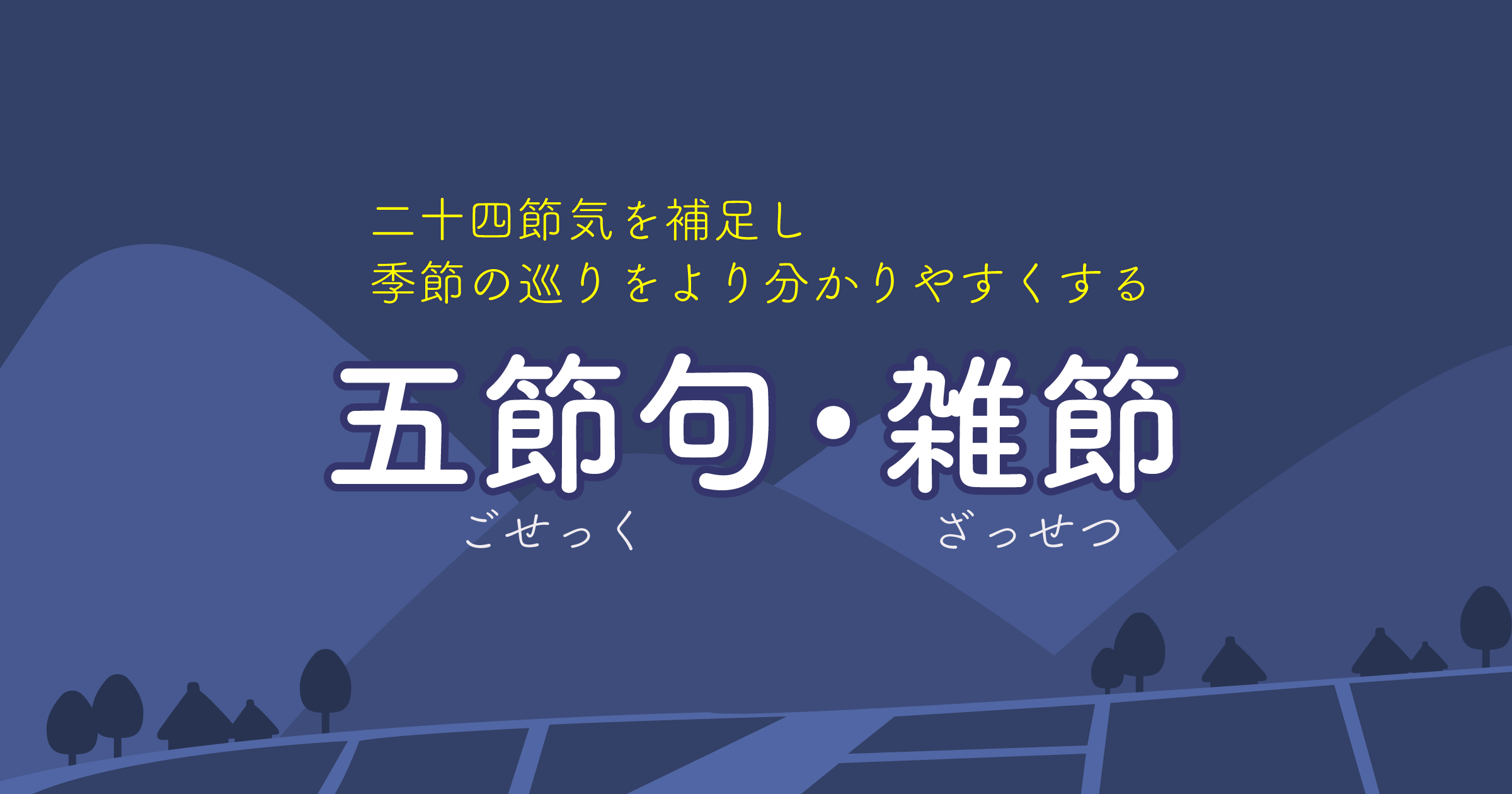立春(りっしゅん)
- 2月4日頃
- 黄経315度
旧暦正月の正節。二十四節気においては最も重要とされる新しい年の一日目。
暦の正月一日と二十四節気の立春が一致することは少ない。
雑節の八十八夜や二百十日などはこの立春を基準から数えられ、農業の目安とされた。
寒さもピークとなり、少しずつ春の兆しが現われてくる頃。
立春の七十二候
初候:東風解凍
【時期】2月4日~8日頃
【読み】はるかぜこおりをとく/とうふうこおりをとく
【意味】東から暖かい風が吹き始めて氷を解かす

東風とは、東寄りから吹くやや冷たさを感じる早春の風のことです。四月頃まで吹くので春の季語とされています。
ちなみに春の訪れを告げる風といえば「春一番」がありますが、これは立春から春分までの間に、その年最初に吹いた、暖かく強い南寄りの風(南風)のことを言います。
まだまだ寒いニ月を春の始まりとしたのは、古代中国の陰陽五行思想にある「陰極まって陽に転ず」という考え方から連想して、厳寒の時期にこそ春の始まりを感じたからとされています。
また春の気は「木」であらわされ、東という字は木立の間から陽が昇る様子を示していると言われているため、概念上「春になる」この時期に東風が吹かねばなりませんでした。
次候:黄鴬睍睆
【時期】2月9日~13日頃
【読み】うぐいすなく
【意味】うぐいすが鳴き始める

春告鳥ともいわれるウグイス。その年初めてのウグイスの鳴き声のことを「初音」とも言い、春の季語となっています。
ちなみに、ホーホケキョと鳴き、褐色がかった渋みのある茶色(鶯茶色)の羽色をしたのが「ウグイス」で、頭から背中にかけて黄緑色をした目の周りが白いのは「メジロ」です。
古代中国では立春の次候は「蟄虫始振」でした。すごもりしていた虫が動き始めるという意味ですが、現在の七十二候においては「啓蟄」の初候「蟄虫啓戸」となっています。
末候:魚上氷
【時期】2月14日~18日頃
【読み】うおこおりをいずる
【意味】溶けはじめた氷の間から魚が出てくる

冬の間は氷の張った冷たい水の中でじっと隠れていた魚も、川や湖の水温が上がり氷が解け始めると、春の兆しを感じて元気に動き始めます。
「氷のあいだから魚が飛び出てくる」と説明されることも多いのですが、「薄くなった氷の下に魚が泳ぐようすが見え始める」というニュアンスです。
この頃から、各地で渓流釣りが解禁となります。