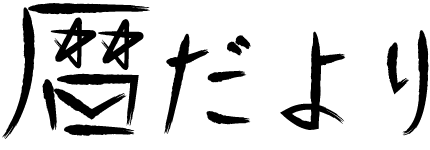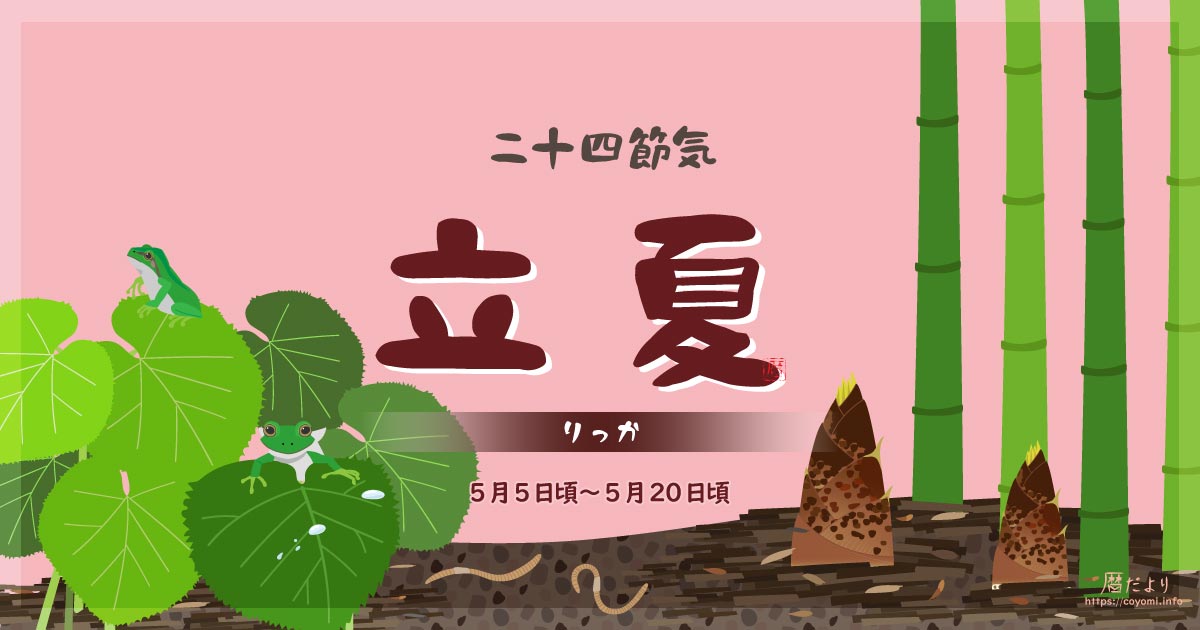立夏(りっか)
- 5月5日頃
- 黄経45度
春の柔らかい日差しが少しずつ力強くなり、草木の緑が色濃くなる頃。
暦の上では夏が始まるとされる日。しかし二十四節気は四季が同じ日数なので実際の季節とはズレが生じる。そのため立夏の頃に様々な花が咲き始めようやく春爛漫となる地方もあれば、陽光に映える新緑や気温の上昇に初夏を感じ始める地方もある。一般的には、入梅の前ごろを春の終わりとすることが多い。
立夏の七十二候
初候:蛙始鳴
【時期】5月5日~5月9日頃
【読み】かわずはじめてなく
【意味】田んぼでカエルが繁殖し鳴き始める

春先に冬眠から目覚めた蛙が元気に活動を始める頃。田んぼに水が引かれ雨が多くなる5月頃(地方によっては7月)から、アマガエルやウシガエル、トノサマガエル、ダルマガエルなど多くの種類のカエルが繁殖期を迎えます。(※一部の種類は、1~2月の寒い時期や3~4月の早春に繁殖期を迎えますが、大半は5月~7月)
鳴くのはオスの蛙だけで、産卵の準備が整ったメスに選んでもらうために大声で競うように鳴きます。求愛の他に、危機への警戒や縄張りの主張、また自分がオスであることを相手に分からせる目的でも鳴いているそうです。
陸にすむ脊椎動物の中で尻尾がないのは、人間や類人猿以外では蛙だけです。また地球上で最も繁栄している両性類で、南極大陸を除いた世界中に約4,000種以上の蛙が生息しています。そのため、蛙は古くから身近な存在として意識されてきました。擬人化して描かれることも多く、ことわざや慣用句に登場したり、蛙を題材とした作品が様々な分野でつくられるなど、日本だけでなく世界中の文化に深く根づいています。
次候:蚯蚓出
【時期】5月10日~5月14日頃
【読み】みみずいずる
【意味】畑などでミミズが地上に這い出てくる

ミミズは目と手足がない紐状の動物で、「目見えず」から「メメズ」になり、転じて「ミミズ」になったともいわれています。ミミズには目がありませんが、体表には微小な視細胞が散在していて、光の方向を感知することができます。光を感じるとミミズは逃げるように土に潜る習性があります。
ミミズが土中を進むことで土が掘り起こされ、その通り道によって深いところまで酸素や水がいきわたります。そのため日本ではミミズを「自然の鍬」と呼ぶこともあります。
ミミズは落ち葉などの有機物や微生物、小動物などが含まれた土を食べます。それらを消化吸収し、窒素やリンを含む粒状の糞として排泄しますが、これが特に植物の生育に適しているため、農業ではミミズを土壌形成の益虫として扱っています。
また大気中の炭素は、植物から土壌を経て約12~20年で再循環するといわれていますが、それらは土中にいる虫の腸を通じて処理されます。進化論で有名なチャールズ・ダーウィンは「植物が生えている土はミミズの体を何度も通ってきている」と述べており、生物学に精通していた古代ギリシャのアリストテレスはミミズを「大地の腸」と言い表していました。
英語では「earthworm(地球の虫)」というミミズは、地球の歴史においてとても重要な役割を果たしてきたのです。
末候:竹笋生
【時期】5月15日~5月20日頃
【読み】たけのこしょうず
【意味】竹やぶでタケノコが生えてくる

タケノコ(筍)は竹の地下茎から出てくる若い芽のことです。
冬に地温5度以下になると生育を停止し、地温5度を超えるようになる早春頃に再び成長し始め、地温が10度に近づく頃に地表に顔を出すようになります。
一般に食べられているのは、柔らかくてエグみが少ない「孟宗竹」という中国原産のタケノコで、3月中旬ごろから出回ります。また灰汁が少なく食べやすい「淡竹」は4月頃です。そのため5月頃はもう旬の終わりと思われますが、日本原産の真竹は5~6月頃に旬を迎えます。そのため七十二候の「竹笋生」は真竹のことだと言われています。
孟宗竹は地下茎が深いため地表から出る頃にはエグみが出始めるので、地中にあるものを掘り探します。つまり「たけのこ堀り」をするのは孟宗竹です。淡竹は地下茎が浅く地表に出きたのものを採ります。生長してすぐに地表に現れるのでエグみは少ないのですが、地面の中の部分はとても硬くて食べられません。真竹は淡竹と同じで地下茎が浅いため、地表に出てきたものを採って食べます。