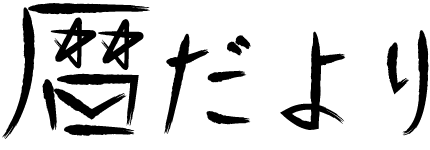啓蟄(けいちつ)
- 3月6日頃
- 黄経345度
「啓」はひらく、「蟄」は冬眠するという意味がある。秋に巣ごもり、冬の間は土の中に隠れていた虫たちが春の気配を感じて地上に這い上がり始める頃。
啓蟄の七十二候
初候:蟄虫啓戸
【時期】3月6日~10日頃
【読み】すごもりのむしとをひらく
【意味】巣篭っていた虫が外に出始める

この頃は、春一番のような強い風が吹いたり天気が不安定になりがちで、雷がひときわ大きく鳴ることから、巣ごもりしていた虫たちが雷の音に驚いて出てくると考え、この春雷のことを「虫出しの雷」ということもありました。
次候:桃始笑
【時期】3月11日~15日頃
【読み】ももはじめてさく
【意味】桃の花が咲き始める

暦のズレから、ひな祭りに合わなくなった桃の花がようやく咲き始める頃です。
ただし梅・桃・桜などは、北海道と沖縄では咲く時期がかなりズレるので、地方によって花の開花と季節感には違いがあります。
桃は邪気を祓ったり、不老長寿を与えるなどといわれ、めでたい植物とされていました。
末候:菜虫化蝶
【時期】3月16日~20日頃
【読み】なむしちょうとなる
【意味】菜虫(青虫)が、さなぎから羽化して蝶になる

サナギの状態で越冬した菜虫の幼虫が羽化して紋白蝶となり、ふわふわと飛び回っている頃です。
菜虫とは、キャベツや大根などアブラナ科の葉につく虫の総称です。