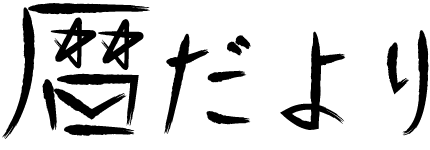芒種(ぼうしゅ)
- 6月6日頃
- 黄経75度
熟した麦を刈り取って、その後に稲を植える頃。
「芒」とは、麦やコメなどの先端の細い毛のこと。芒種とは、そうした穀物の種を蒔くころのことで、梅雨の前に田仕事に追われるため、農家は多忙を極める時期となる。
暦の上の入梅は、むかしは「芒種の後の最初の壬の日」として規定していたが、現在は太陽が黄経80度に達した時とされる。気象上の入梅は、梅雨前線の北上によってもたらされる。
芒種の七十二候
初候:蟷螂生
【時期】6月6日~10日頃
【読み】かまきりしょうず
【意味】かまきりが生まれる
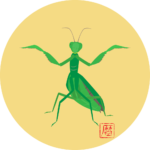
秋に産み付けられ、冬を越したカマキリの卵が孵化するころです。一つの卵のかたまりから、300匹近くの小さな子カマキリが一斉に生まれます。
カマキリはオスに比べてメスの方が大きく、オスは飛べますがメスは飛ぶことができません。
カマキリは害虫を捕まえてくれるため益虫として扱われることもありますが、実際は見境なく食べているだけで、成長にともなって捕食する虫の大きさを変えていきます。卵からかえった幼虫たちは、アブラムシや蟻などを食べ、成虫になるとバッタや青虫など大きな虫も食べるようになります。特に産卵直前のメスは手当たり次第に捕食します。
次候:腐草為螢
【時期】6月11日~15日頃
【読み】くされたるくさほたるとなる
【意味】腐った草が蛍となる

蛍は別名「朽草」とも呼ばれ、昔の人は「腐った草が蛍になる」と信じていたそうです。
蛍の幼虫は、水中から陸に上がって湿った土の中でサナギになり、やがて羽化すると地上に現れます。湿って腐った枯草のなかから出てくるのを「腐った草が蛍に化生する」と表現したのでしょう。
蛍は腹部の後方が発光することで知られている昆虫です。卵や幼虫時代はほどんどの種で発光しますが、成虫になると発光するのは夜行性の種が大半を占めます。蛍が発光するのは「敵への威嚇や警告」「交尾のための交信」「捕食のための誘引」などの説があります。
また蛍の成虫は、口器が退化していて水分を摂取することくらいしかできません。そのため約1~2週間の間に、幼虫時代に蓄えた栄養素のみで繁殖活動を行います。
末候:梅子黄
【時期】6月16日~6月20日頃
【読み】うめのみきばむ
【意味】梅の実が黄色く色づく

大きく実った梅の実が、黄色くなって熟すころです。「梅雨」の語源は「梅の実が熟するころの雨」ともいわれています。
6月上旬〜中旬は、青い梅の収穫です。青梅は酸味が強いため梅酒やシロップ漬けに利用します。6月下旬になると黄色く熟した梅が収穫されます。この熟して柔らかく甘味が出てきた梅を使って、梅干しやジャムがつくられます。
梅は、奈良時代に「烏梅」という健胃整腸の薬として中国から伝わり、風邪薬や胃腸薬として用いられました。烏梅は、青梅の実を籠に入れて釜戸で燻し乾燥させたもので、烏のように真っ黒だったことから「烏梅」という名前がつけられたそうです。烏梅はクエン酸を多く含むため、ベニバナから「紅色素」を取り出すための媒染剤としても利用されました。
平安中期ごろに書かれた、日本の最古の医学書である「医心方」には、「梅は三毒を断ち、その日の難を逃れる」と書かれています。三毒とは「食べ物の毒(食中毒を起こす細菌)」「血液の毒(疲労のもととなる乳酸など)」「水の毒(水に含まれる病原菌)」のことです。
梅に含まれるクエン酸には抗菌・整腸・解毒の作用があり、疲労の原因物質となる乳酸を分解してくれます。また梅に含まれているミネラル(カリウム、マグネシウム、カルシウムなど)は不要な水分を除去する作用があるため、むくみ解消になったり、唾液の分泌が促進されることで消化を助けてくれたりします。