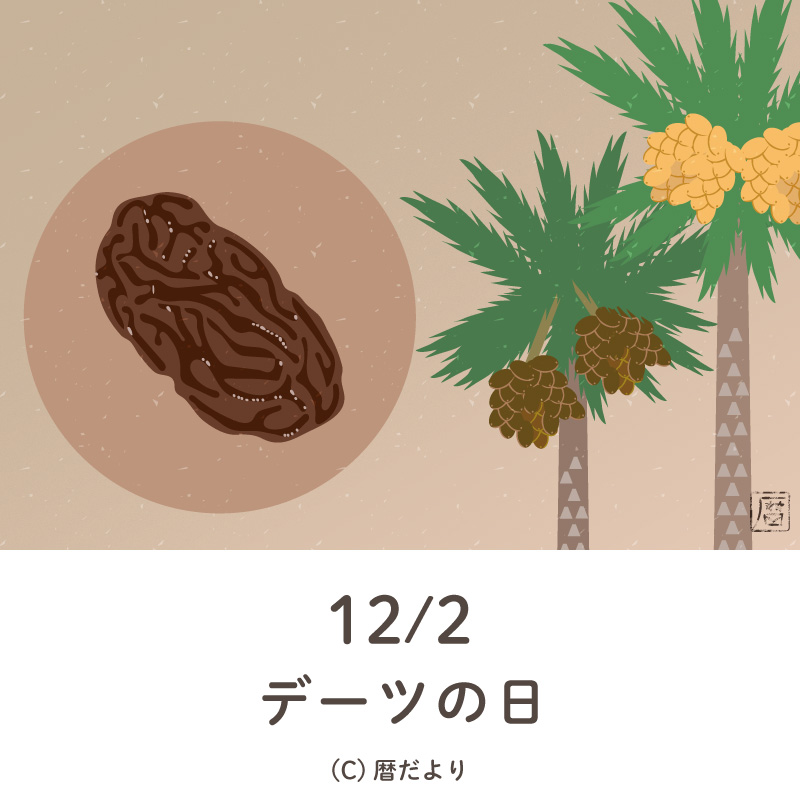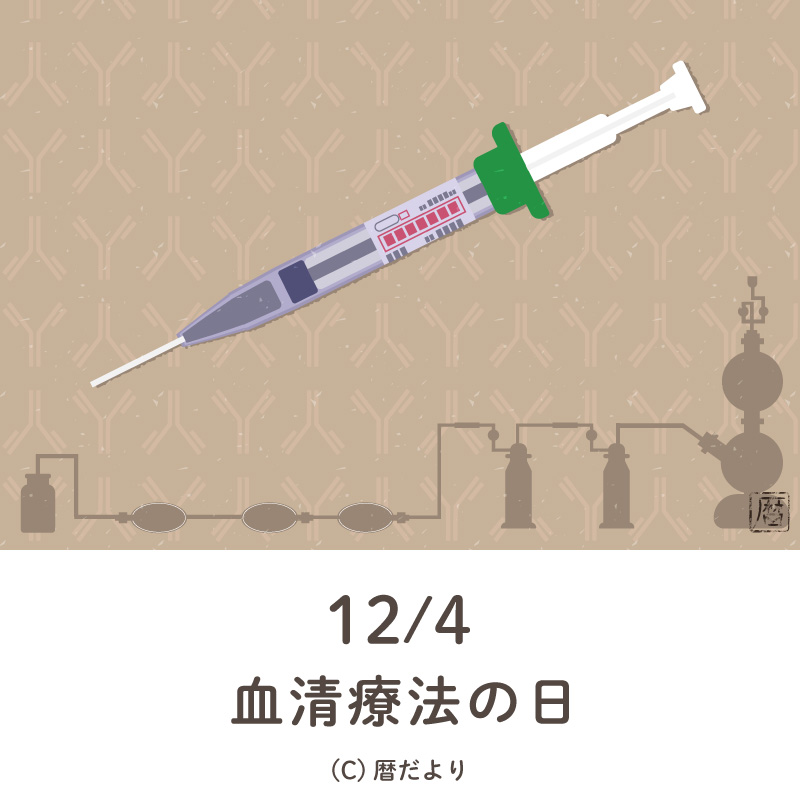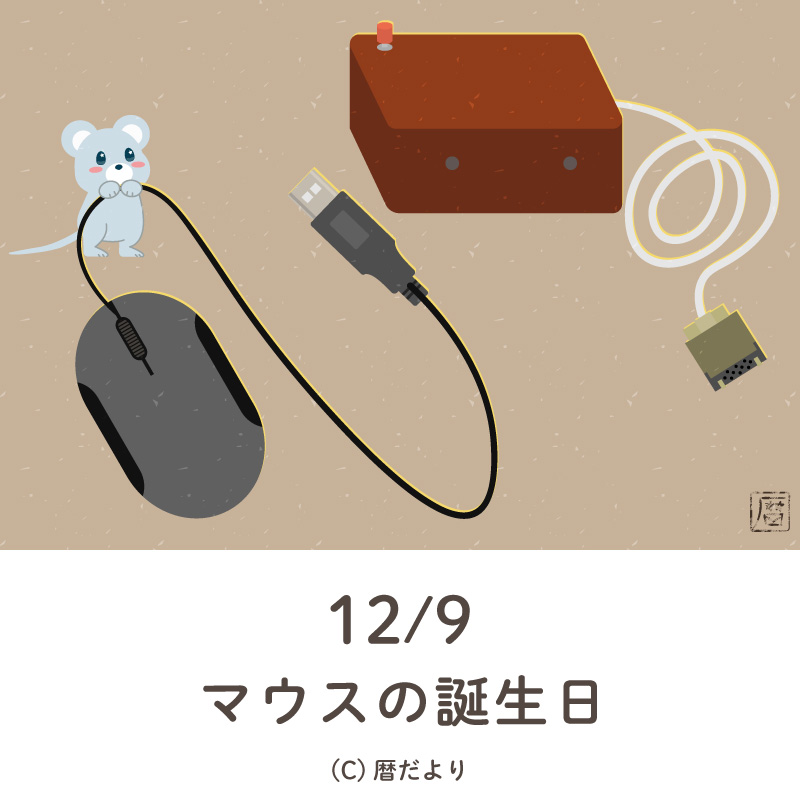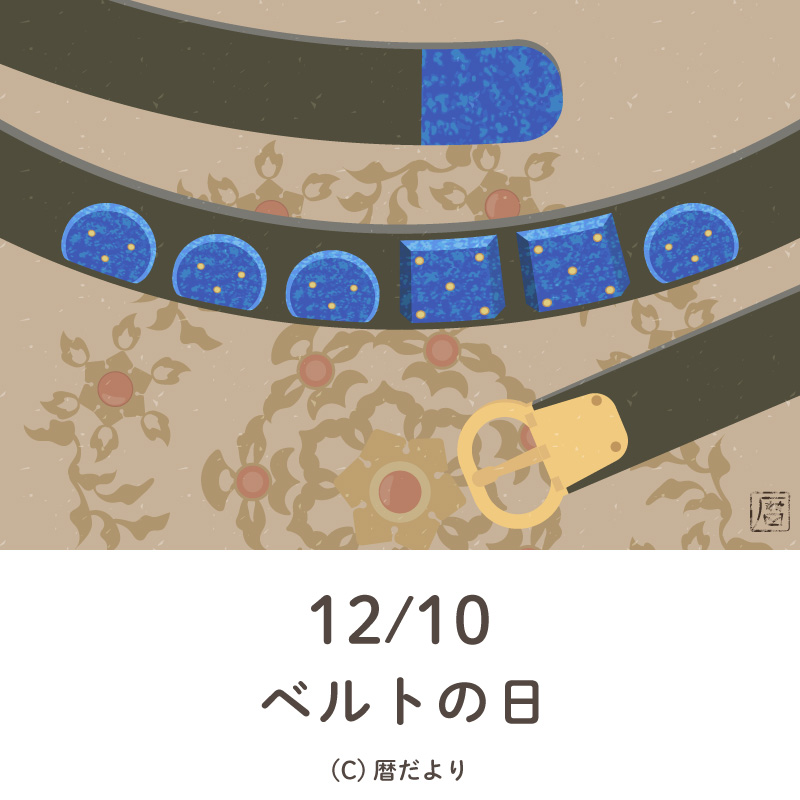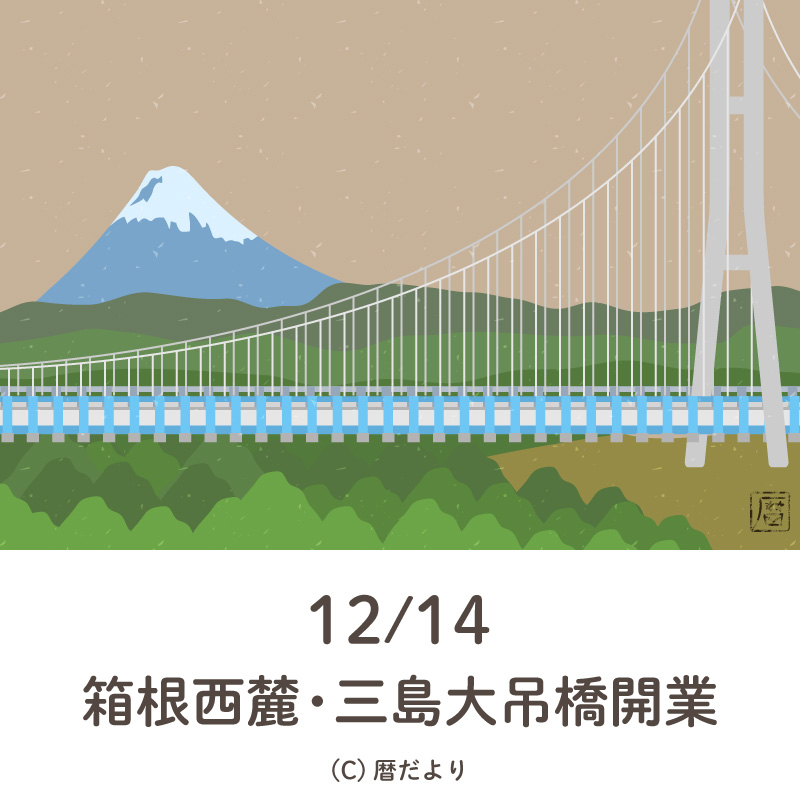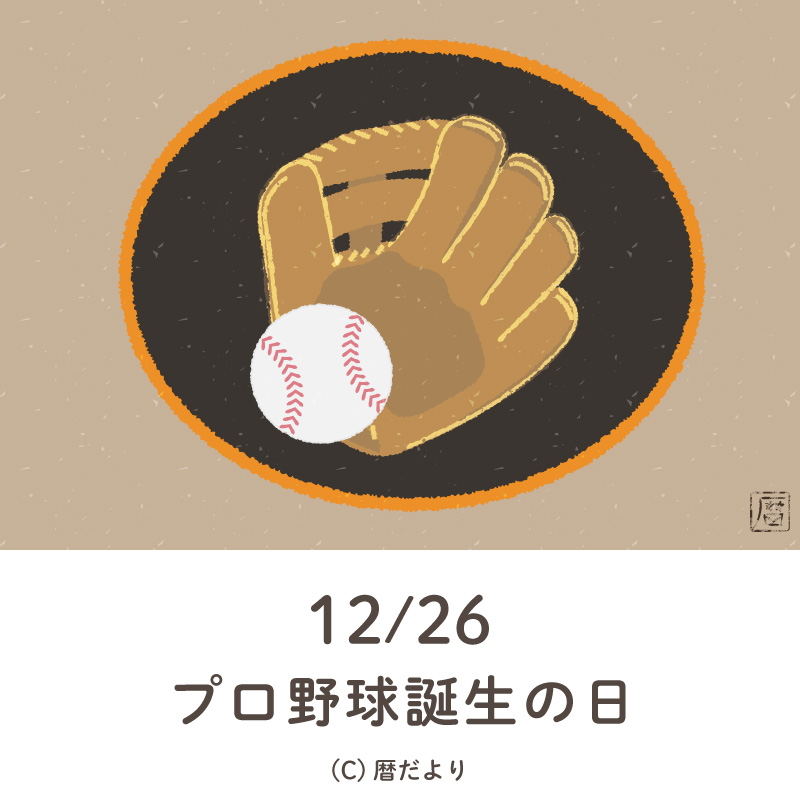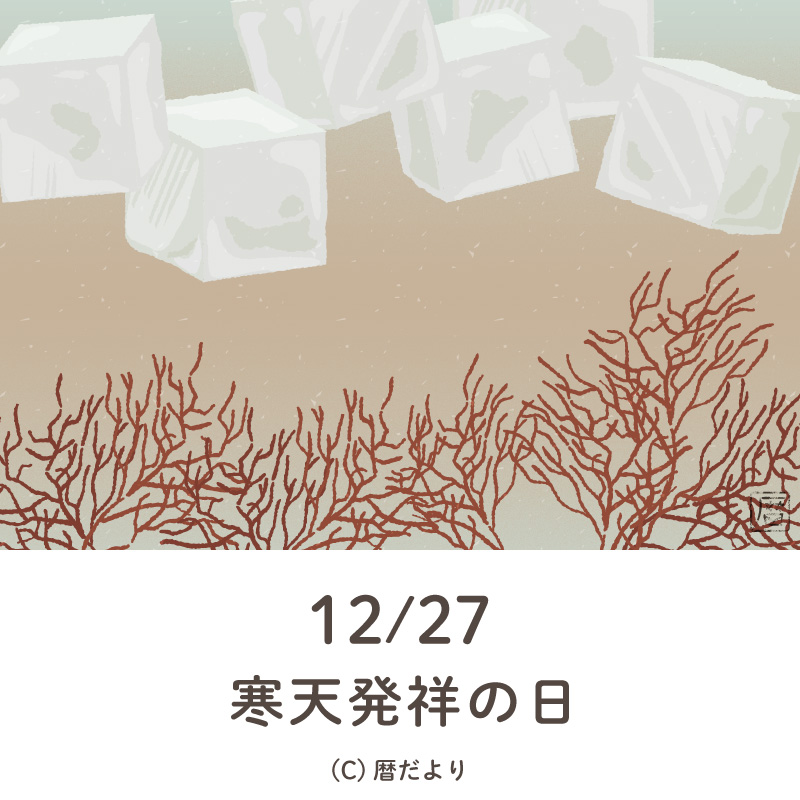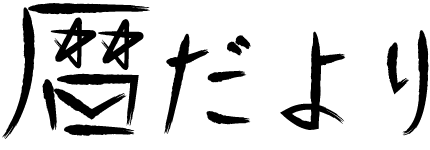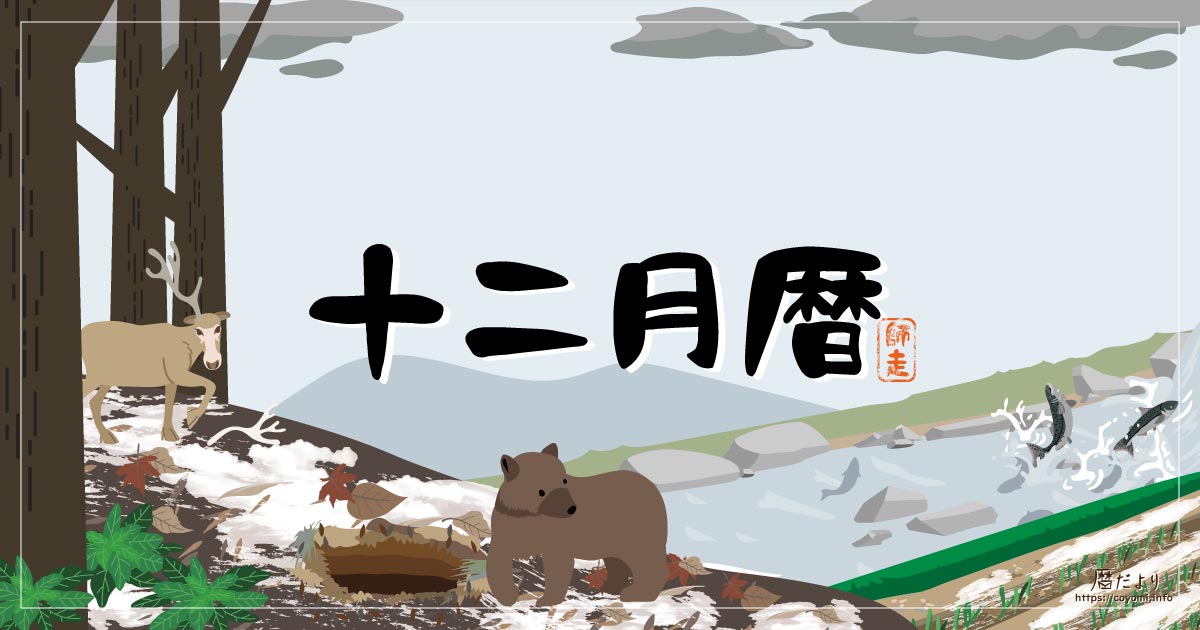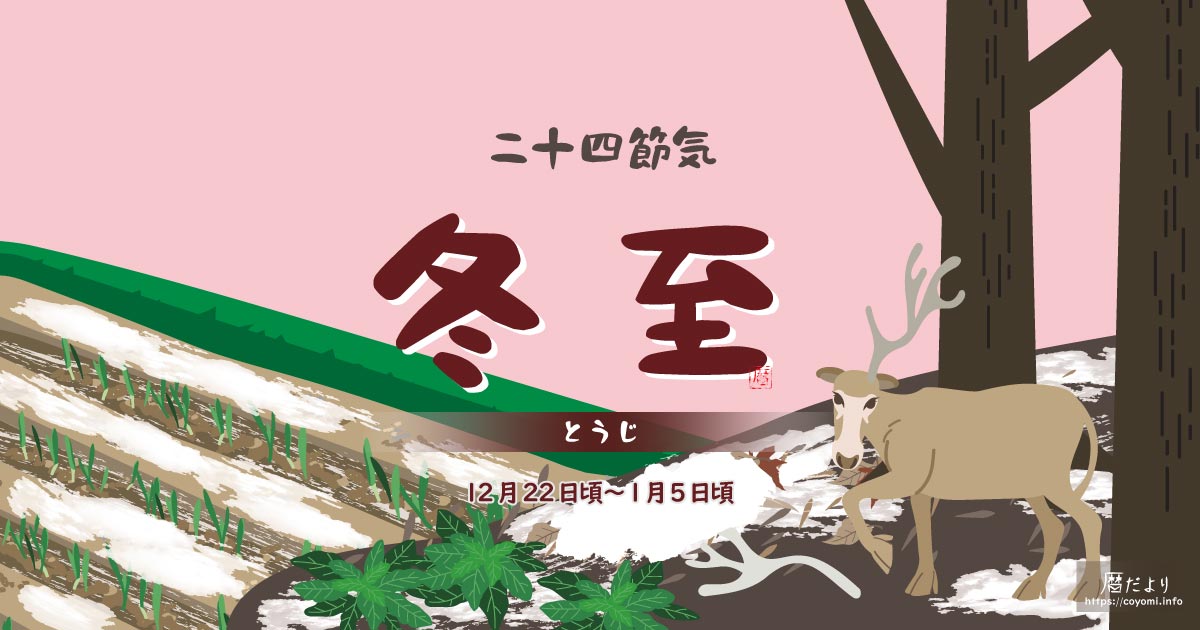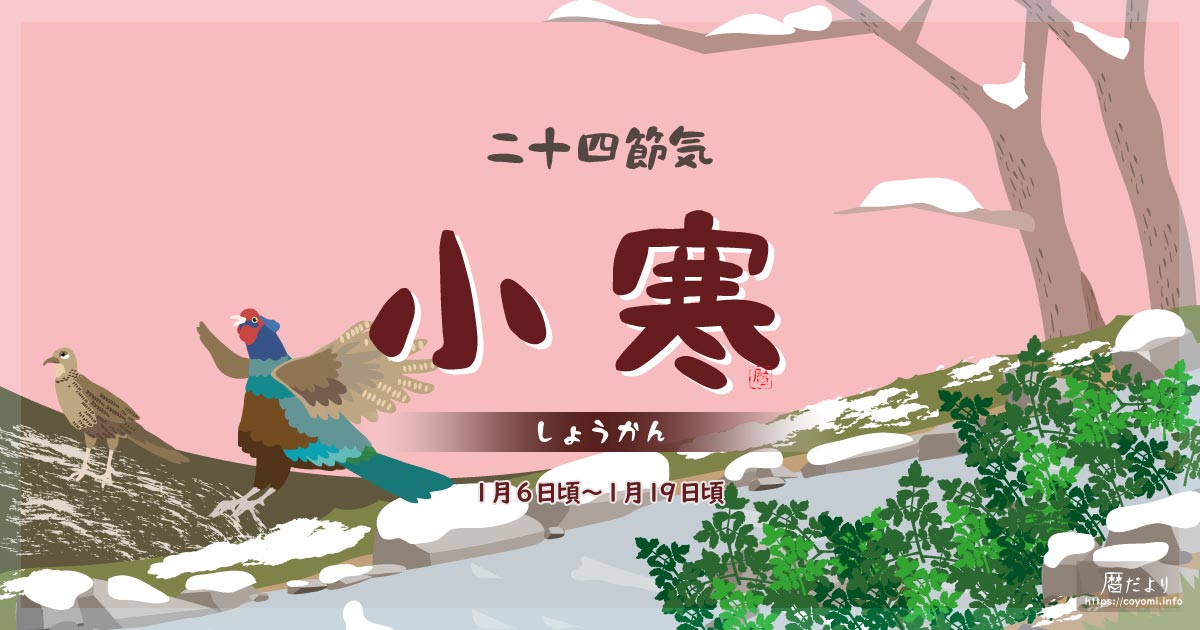十二月の異名(和風月名)
法師が読経などのために東西に馳せまわる月ということで「しがはせる」から「しわす」になったという説や、「師馳せ月(しはせづき)」が誤って「師走」になったなど由来には諸説あります。年末にその年の罪を懺悔し清める「仏名会」という法要が行われたり、年末年始に先祖供養をする家が多いため、12月は法要が集中していました。
- 師走(しわす)
- 晩冬(ばんとう)
- 氷月(ひょうげつ)
- 黄冬(おうとう)
- 弟月(おとづき/おととづき)
- 乙子月(おとごづき)
- 親子月(おやこづき)
- 限月(かぎりのつき)
- 極月(ごくげつ)
- 暮来月(くれこづき)
- 建丑月(けんちゅうげつ)
- 丑の月(うしのつき)
- 丑月(ちゅうげつ)
- 春待月(はるまちつき)
- 暮歳(ぼさい)
- 臘月(ろうげつ)
- 苦寒(くかん)
- 歳極月(としはすづき)
- 三冬月(みふゆづき)
- 梅初月(うめはつづき)
- 暮古月(くれこづき)
- 除月(じょげつ)
十二月の節気
二十四節気
大雪
【12月7日頃~12月21日頃】山では木の葉がすっかり落ちて雪が降り積もり、平地でも本格的に冬の気候となる頃。
冬至
【12月22日頃~1月4日頃】一年でいちばん日が短く、夜が長い日。冬至は冬の真ん中で、この日を境にまた昼が長くなっていく。
十二月の行事と暮らし
行事と暮らし
事八日
2月8日と12月8日の年2回またはいずれか
「事八日」は、祭事や農作業が始まる日または終わる日。正月行事として12月8日を事始め、2月8日を事納めとするところと、一年の農事として12月8日を事納め、2月8日を事始めとするところがある。
2月8日と12月8日の年2回またはいずれかに行われ、どちらかを「事始め」といい、他方を「事納め」と呼びます。
「事」とは、年間に行われる祭事や農作業のことと解釈されるのが主流で、2月を「事始め」12月を「事納め」とする地域が多いのですが、関東の一部では「事」を正月行事(新年の祝い事)と解釈し、12月を「事始め」2月を「事納め」とされています。
事八日は、「お事始め/お事納め」「節供始め/節供納め」「お薬師様」「恵比寿講」などとも呼ばれます。
すす払い
12月13日
お正月を迎えるにあたって、一年分のすすやほこりを払い清めて大掃除をする行事。
江戸時代中期まで使われていた宣明暦(太陰太陽暦)では、12月13日は「鬼の日」という吉日でした。婚姻以外は万事吉とされていたことから、正月を迎える準備を始めるのにふさわしい日とされたようです。
一般的には年末の大掃除として定着していますが、元は年神様(歳徳神)をお迎えするために家の内外を清めるという、お正月準備のはじめとなる行事でした。
すす払いの行事は、「正月迎え」「ことはじめ」「ええことはじめ」などと呼ばれることもあります。
歳の市
12月中旬〜下旬
歳の市とは、12月中旬〜下旬に神社やお寺の境内で開催される市。
歳の市では、しめ飾りなどの正月飾りから食品や日用品など、正月準備に必要なものが売られます。
なかでも有名なのは、毎年12月17日〜19日に東京都の浅草寺で行われる「浅草羽子板市」です。羽子板は厄をはねのける縁起物とされています。
根の先端についている黒い玉は「無患子」という木の実で、子どもの無病息災の願いを込めて羽根つきをしたり、役者や美人画などの押絵細工を施された羽子板を、厄除けや魔除けとして飾ったりします。
終い弘法
12月21日
「終い弘法」とは、一年最後の「弘法市」のことで正月の縁起物などが売られる。
東寺では、弘法大師(空海)の月命日である21日に「御影供」という法要が行われます。その時に参拝者向けに開かれていた露店が、「弘法市」と呼ばれる縁日の始まりだそうです。
一年最後の縁日のことを「終い弘法」と呼び、正月の縁起物や食品・日用品、植木などが売られて賑わいます。
冬至
12月22日頃
冬至は二十四節気の一つで、一年でいちばん日が短く、夜が長い日。冬至は冬の真ん中で、この日を境にまた昼が長くなっていく。
冬至は「一陽来復」ともいわれ、太陽が復活し始める日という意味があります。そのため冬至を境に運も上昇するとされ、カボチャを食べて栄養を付けたり、ゆず湯に入って身体を温め無病息災を願ったりして過ごします。
カボチャ(南瓜)を食べるのは、「ん」が2つある食べ物は運をたくさん取り込むとされているためです。
カボチャ以外にも、「れんこん、にんじん、ぎんなん、きんかん、かんてん、うんどん(うどん)」なども「運盛りの野菜」とされ、「冬至の七草」と呼ばれることもあります。
クリスマス・イブ
12月24日の日没から25日の日没まで
クリスマス・イヴは、「クリスマスの夜」のこと。
日本では「クリスマス(12月25日)の前夜」と誤って認識されていることが多いのですが、クリスマス・イヴは「クリスマスの夜」のことです。
日没を日付の変わり目としている教会暦では24日の日没から25日の日没までが「クリスマス」となります。
クリスマスは、イエスキリストの降誕を記念する祭りで「キリスト(Christ)のミサ(Mass)」というのが語源だそうです。
大晦日
12月31日
一年の最後の日を「大晦日」または「大晦」と言う。
旧暦の頃は月の最後の日を「晦日」と呼んでいて、一年の最後の特別な末日ということで「大晦日」とされました。
大晦日の行事は平安時代ごろから行われ、本来は歳神様を祀るための準備が行われていました。仏教が浸透すると、煩悩を祓うとされる「除夜の鐘」を鳴らす風習が生まれ、江戸時代になって「年越しそば」が食べられるようになりました。
年越しそばの由来は諸説ありますが、蕎麦は他の麺類に比べて切れやすいことから「今年1年の災厄を断ち切る」とされたり、「そばのように細く長く生きれるように」と延命や長寿を願ったりと、縁起を担いで食べられています。
祝日・記念日
今日は何の日