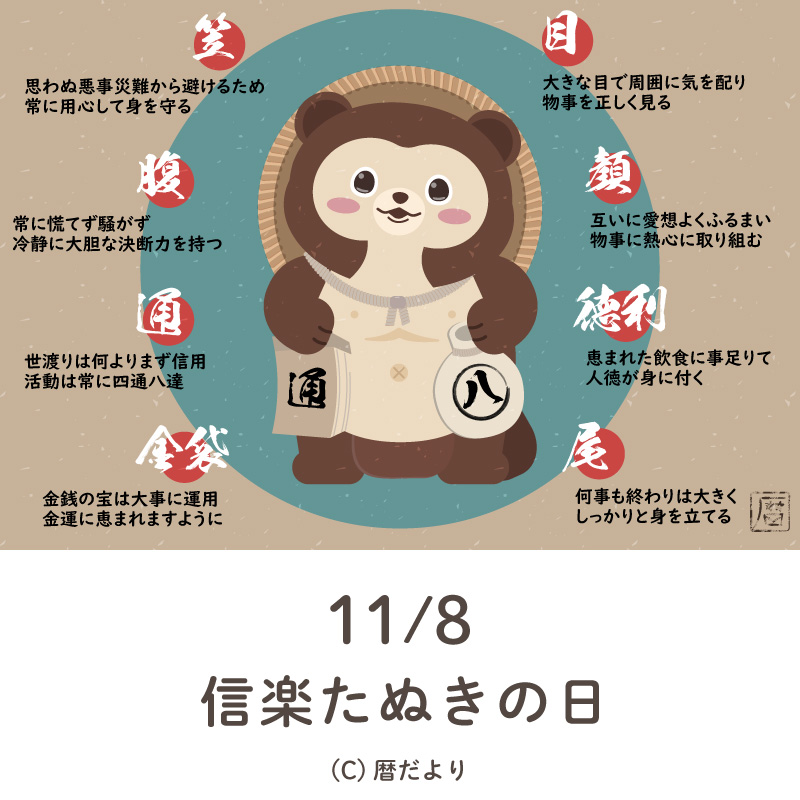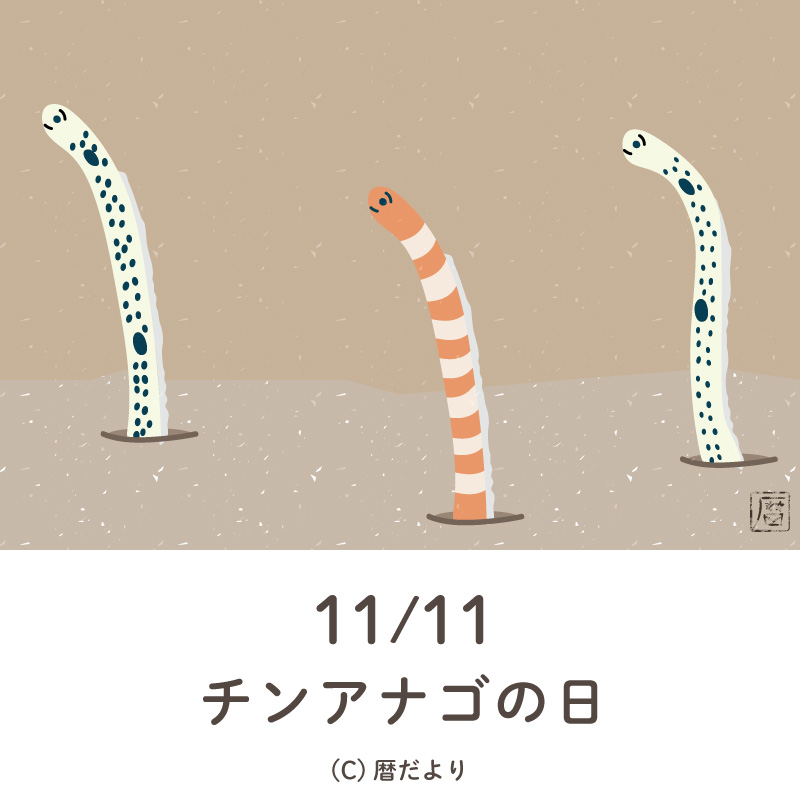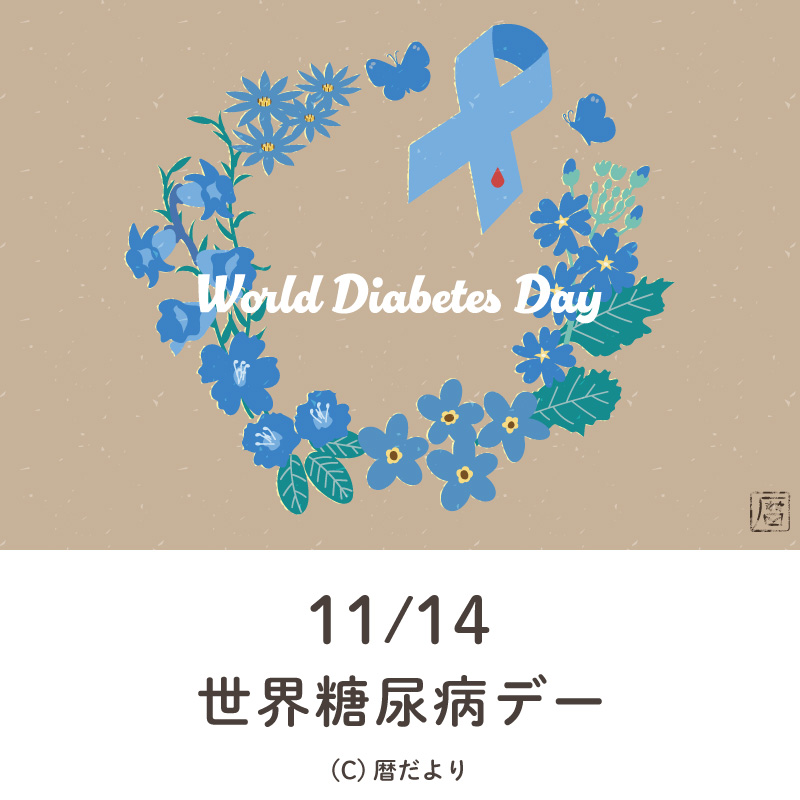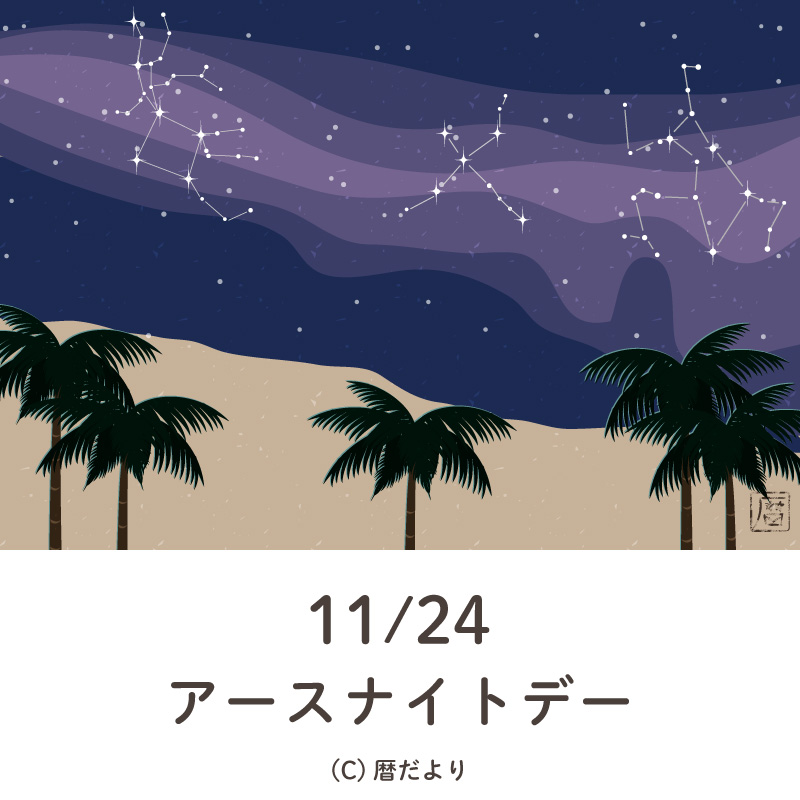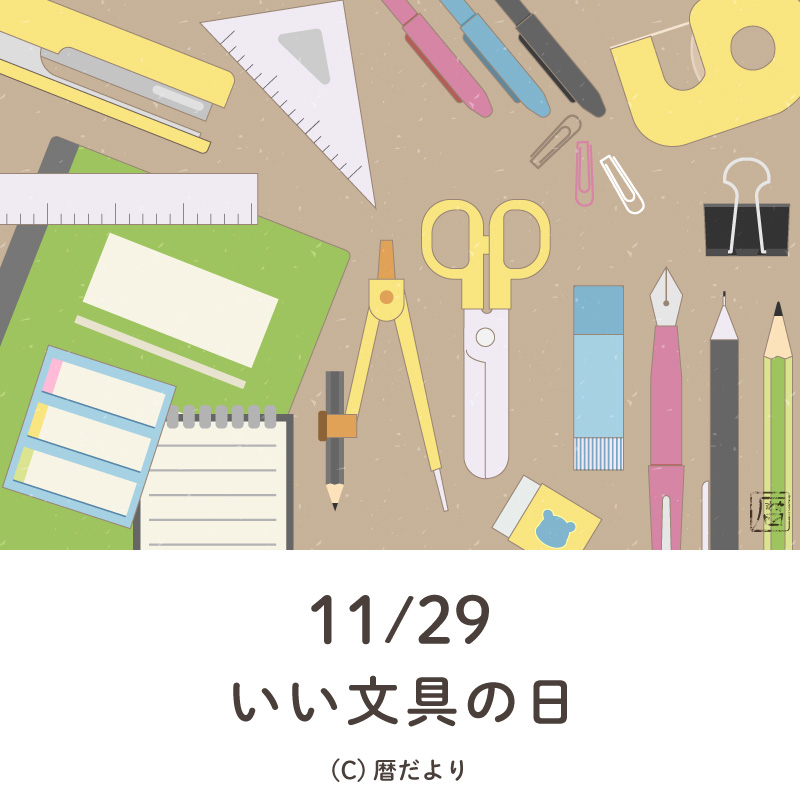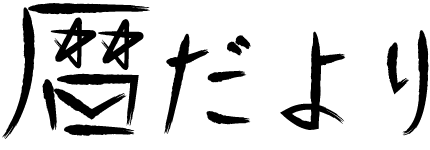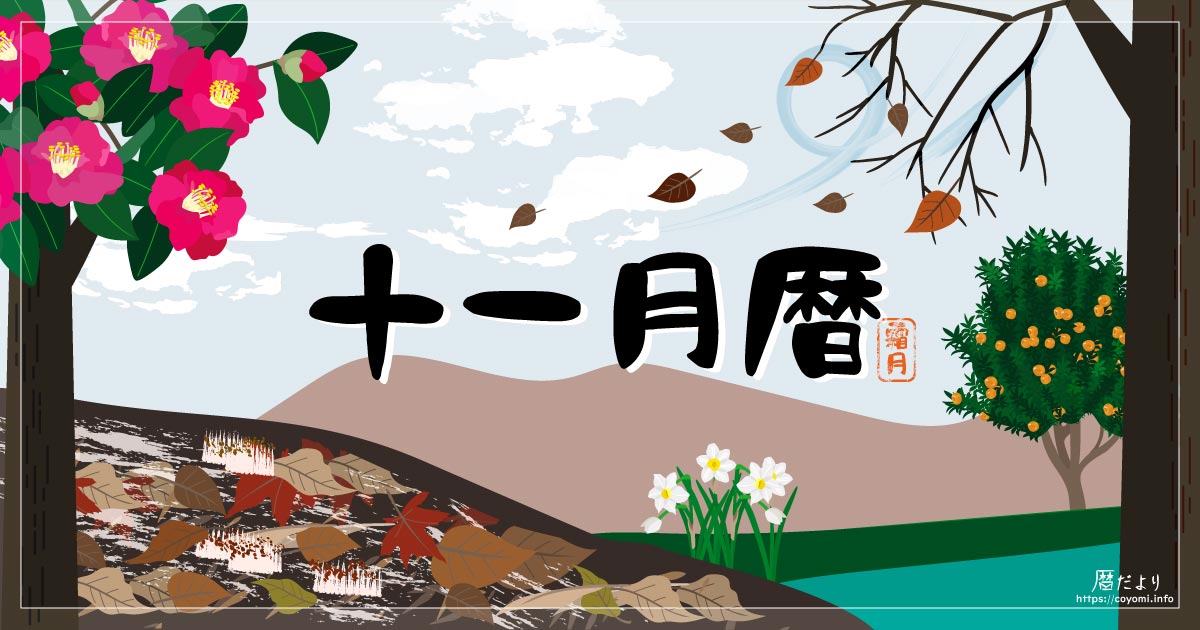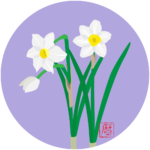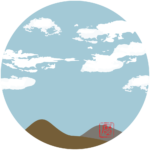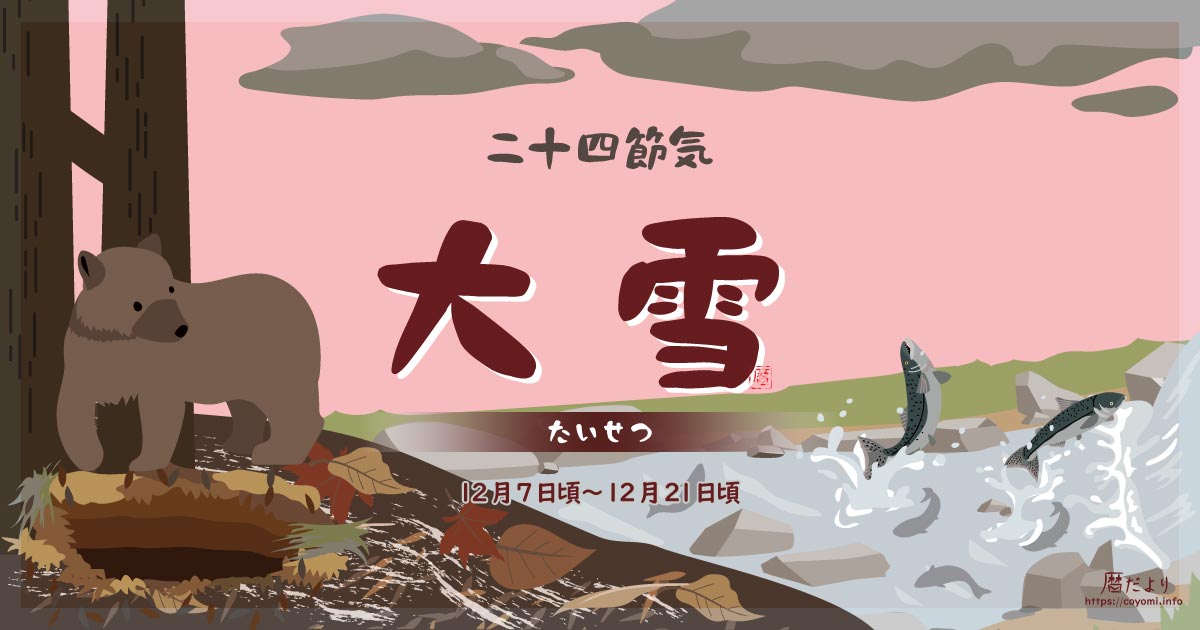十一月の異名(和風月名)
霜が降りるようになる頃で「霜降月(しもふりづき)」から転じたとの説や、本来は「下の月」だった説など、由来には諸説あります。
- 霜月(しもつき)
- 神楽月(かぐらづき)
- 天正月(てんしょうげつ)
- 神帰月(かみきづき)
- 神来月(かみきづき)
- 雪待月(ゆきまちづき)
- 雪見月(ゆきみづき)
- 霜降月(しもふりづき)
- 霜見月(しもみづき)
- 建子月(けんしげつ)
- 陽復(ようふく)
- 復月(ふくげつ)
- 陽復(ようふく)
- 竜潜月(りゅうせんげつ)
- 子月(ねづき/しげつ)
- 暢月(ちょうげつ)
- 達月(たつげつ)
- 露隠月(つゆごもりづき)
- 露隠葉月(つゆごもりのはづき)
- 食物月(おしものづき)
- 凋月(しぼむつき)
十一月の節気
二十四節気
立冬
【11月7日頃~11月21日頃】色付いていた自然が色あせはじめ、木の葉が落ちて積もる頃。
小雪
【11月22日頃~12月6日頃】寒さが増して、山のほうでは雨が雪に変わり始める頃。
十一月の行事と暮らし
行事・暮らし
酉の市
11月酉の日
酉の市は、各地の鷲神社や大鳥神社で行われる開運招福・商売繁盛の祭りに立つ市で、縁起物の「熊手」などが売られる。
11月酉の日に行われる「酉の市」は、各地の鷲神社や大鳥神社で行われる開運招福・商売繁盛の祭りに立つ市のことで、「お酉さま」とも呼ばれています。
もとは「酉の祭」と呼ばれる江戸近郊の農村の収穫祭で、収穫を感謝して村の鎮守の鷲大明神に鶏を奉納したのが始まりでした。奉納された鶏は、祭りのあとに浅草の浅草寺まで運ばれて、観音堂前で放されるそうです。
11月最初の酉の日を「一の酉」、次を「二の酉」、3番目を「三の酉」といいます。鳥の日は12日ごとに巡ってくるので、三の酉がある年とない年があり、「三の酉がある年は火事が多い」ともいわれています。これは「宵に鳴かぬ鶏が鳴くと火事が出る」という言い伝えからだとか、鶏の赤いトサカから連想されたなど諸説ありますが、三の酉の頃には寒さが増して火を使う機会が増えるため、その戒めとして言われるようになったようです。
酉の市の露天では、縁起物の「熊手」などが売られます。熊手は、元は実用的な農具として売られていましたが、落ち葉をかき集めるところから「運をかき込んで、福を取り込む」とされ、お多福や小判、宝船など招福の飾りをつけて縁起物として人気になりました。
小さな熊手から、毎年少しずつ大きな熊手にしていくのが良いといわれ、玄関の入り口に向けて少し高いところに飾ります。
亥の子の祝い
11月第1亥の日、亥の刻
亥の子の祝いは、11月第1亥の日、亥の刻(午後9時から11時)に「亥の子餅」を田の神に供え、家族全員で食べて、無病息災と子孫繁栄を願うならわし。
亥の子の祝いは、主に西日本で行われています。新米で作った餅を田の神に供え、子どもたちは「亥の子搗き」といって、囃ながら丸石を縛り付けた藁の縄で地面をついて、近所から餅をもらいます。地面をつくのは、土地の邪霊を鎮めたり精霊に力を与える豊作のおまじないだそうです。
「十月亥の日亥の刻に餅を食べると病気にならない」という、中国の言い伝えに基づいたもので、亥の子餅は「大豆、小豆、ささげ、ごま、栗、柿、糖」を混ぜてつくられました。日本には平安時代に貴族の間で広まり、宮中では「イノシシの形」が重視されました。
農村ではイノシシの子を田の神と信じられていたことや、ちょうど収穫の時期だったため、次第に収穫祭の意味合いが強くなり、古くからおこなわれていた刈上げ祭などと合わさって農村部に広まりました。民間では「ゴマ(黒)、小豆(赤)、栗(白)」の三色餅や牡丹餅、普通の丸餅など、地域によって様々な亥の子餅がつくられます。
東日本でも亥の子の祝いと同じような行事が行われてきました。「十日夜」は、田の神が山へ帰る日に、田の神の化身とされる案山子を祀り、「案山子上げ」といってその笠を焼いて焼き餅をつくって供える風習です。また、餅を背負ったカエルをお供にして案山子が天に昇るという伝承から、子どもたちが藁を蒔いた棒で唱え言を歌いながら家々の地面を叩いてまわる、亥の子搗きとよく似たならわしもあります。これは太縄で地面を叩くことでモグラを追い払い、収穫に感謝するものだそうです。
七五三
11月15日
七五三は、子どもの節目の年に氏神様や神社にお参りして、子どもの健やかな成長を願う行事。
男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳のときに行います。本来は数え年でおこないますが、今は満年齢で祝う事も多いようです。
「七、五、三」で祝うのは「奇数は縁起が良い」という中国の陰陽思想の影響を受けていて、この節目に成長を祝うことで厄を祓うとされました。
室町時代から宮廷や武家では、3歳で髪を伸ばし始める「髪置き」、男の子が5歳で袴をつける「袴着」、女の子が7歳で着物の付け紐をやめて大人と同じ帯を締める「紐解き(帯解き)」などの儀式が行われていました。明治のころにこれらの儀式と統合されたのが現在の七五三で、全国に広がったのは戦後だといわれています。
七五三が広まった背景には「七つ子祝い」がありました。これは「七つ前は神様」という伝承に基づいたもので、昔は死亡率が高かったので、7歳を成長の節目としていました。
7歳までは神の庇護下にあるので何をしてもバチはあたらず、もし死亡した場合でも大人のような葬式はしなくてよかったそうです。そして、7歳になったら氏神様に詣で氏子の仲間入りをしました。
もとは地域によって日取りが違いましたが、江戸時代後期になって「11月15日」と定められたようです。その由来は、5代将軍徳川綱吉の子である徳松の袴着の儀式を行ったのが「11月15日」だったとか、陰陽道に由来するとか諸説ありますが、秋の収穫後、神をまつる霜月のちょうど真ん中にあたるからという説が有力ともいわれています。
ボジョレーヌーボー
11月第3木曜
ボジョレーヌーボーとは、フランスのボジョレー地方で、その年に収穫したブドウを使用し造られる新酒のこと。世界同時に解禁される。
ボジョレーヌーボーとは、「ボジョレー地方の新しいワイン」という意味です。
フランスのボジョレー地方でその年に収穫されたガメイ種のブドウからつくられた、出来立てのワインをさします。発酵させる期間が通常のブドウよりも短いため、フレッシュでフルーリーな味わいが特徴で、熟成された渋みが苦手な人でも美味しく飲めることで人気です。
しかし熟成が出来ないぶん、その年のブドウの出来具合によって味が左右されやすく、猛暑の年は甘みが増すといわれています。
祝日・記念日
国民の祝日
文化の日
11月3日
「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨とした国民の祝日。
もともとは中国に由来する「天長節」という天皇誕生日でした。日本では775年に光仁天皇が自らの誕生日を祝したという記録がありますが、その後は行われておらず、1868年になって再興されて、1873年の改暦で「天長節」は国家の祝日となりました。
1927年に明治天皇の誕生日にちなんで11月3日が祝日となり、名称も「明治節」と改められています。
その後、1948年に公布施行された「国民の祝日に関する法律」によって「明治節」は廃止され、天皇の誕生日を祝う祝日は「天皇誕生日」となりました。
また11月3日は、1946年同日に日本国憲法が公布されたことを受けて「文化の日」と定められました。「文化の日」という名称には、「戦争放棄を謳った新憲法の精神に基づいて平和を図り、文化を進める」という意味が込められているそうです。
ちなみに、憲法が施行された5月3日は「憲法記念日」となっています。
勤労感謝の日
11月23日
「勤労をたつとび、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう」ことを趣旨とした国民の祝日。
日本では旧暦11月の第2卯の日に「新嘗祭」という祭事がおこなわれていました。これは「天皇がその年に収穫された新穀を神に供えて感謝し、これらの供え物を神からの賜りものとして自らも食する」という儀式で、重要な宮中行事でした。改暦の際にズレを考慮されずに行われたため、現在も11月23日に各地の神社で行われています。
戦後、日本国憲法が改められて国民の祝祭日が見直される際に、祝祭日から国家神道の色を払拭する方針としましたが、「新嘗祭」は「新穀の収穫を感謝する」というものだったので、名称を変えることになりました。
はじめは「感謝の日」という案もあったそうですが、何に対する感謝か分かりにくいということで「勤労感謝の日」となったそうです。
農業の収穫など物品の生産を行うものだけではなく、様々なサービス産業も含めた、物質的にも精神的にも広い意味での文化財を建設してゆくことを「生産」と考えるということで、「勤労」とされました。
今日は何の日