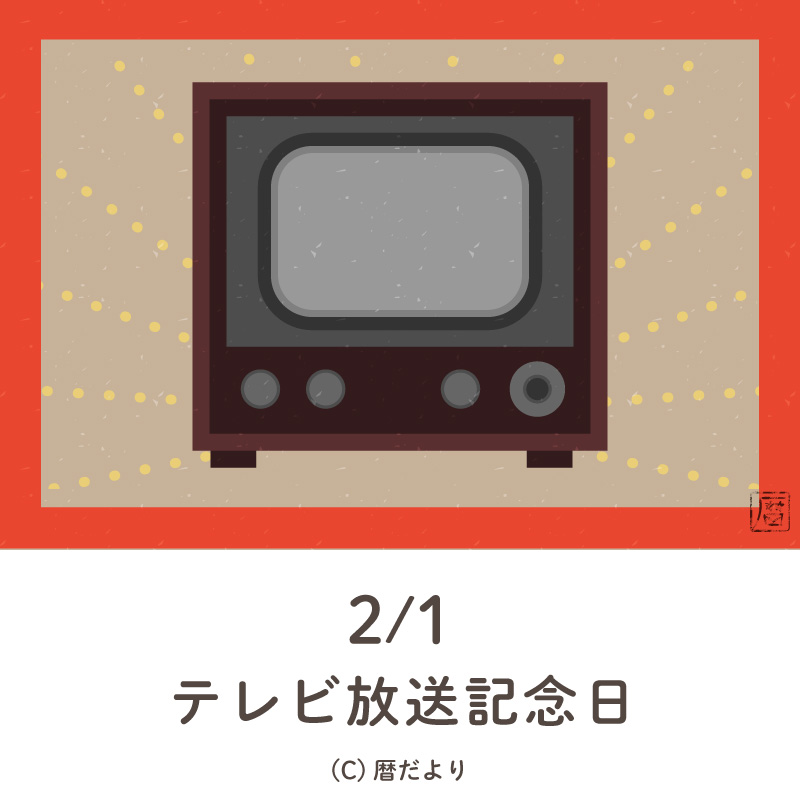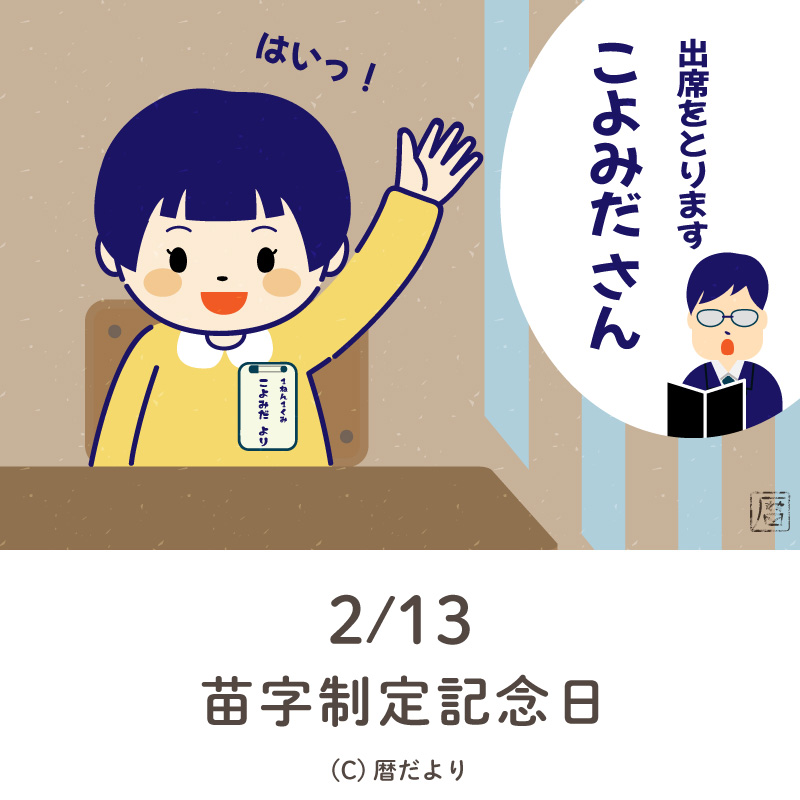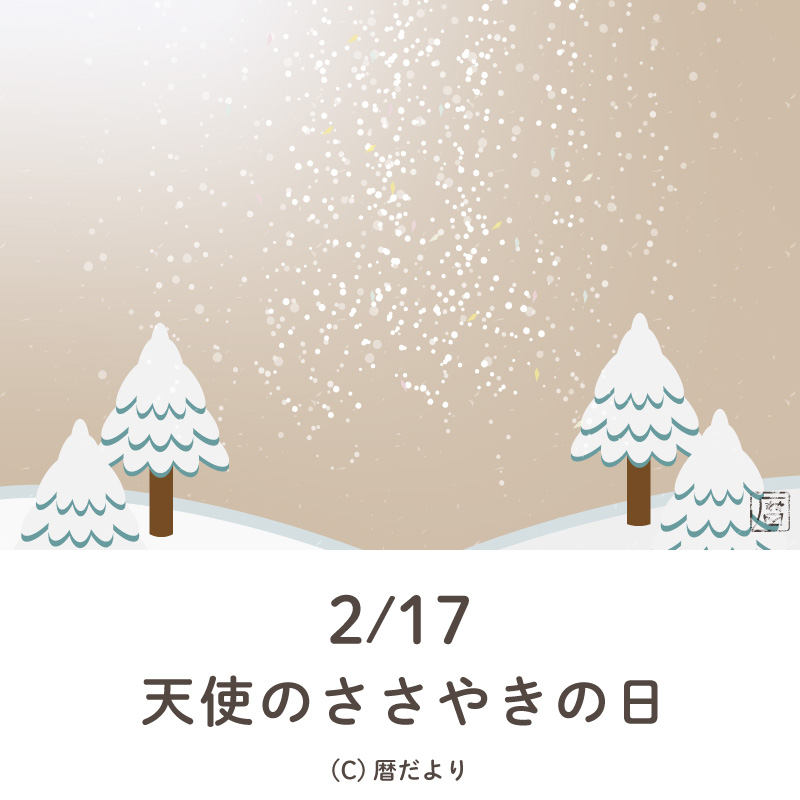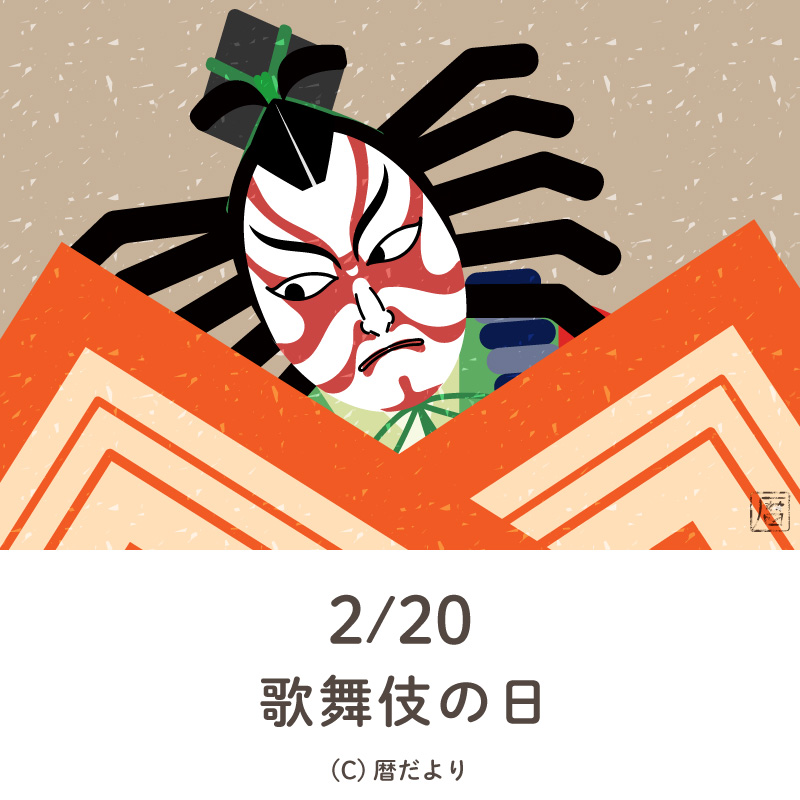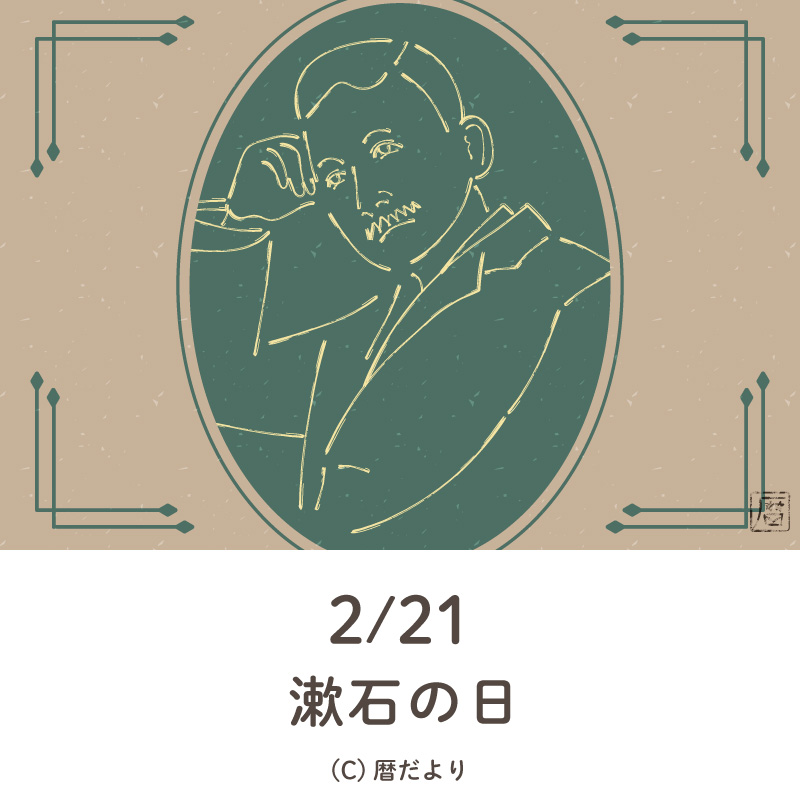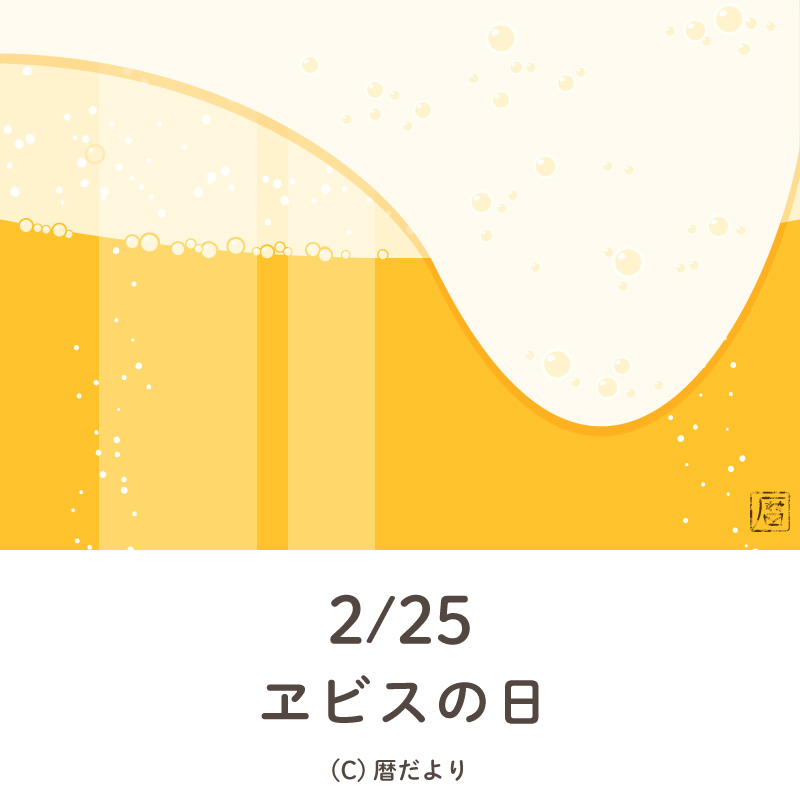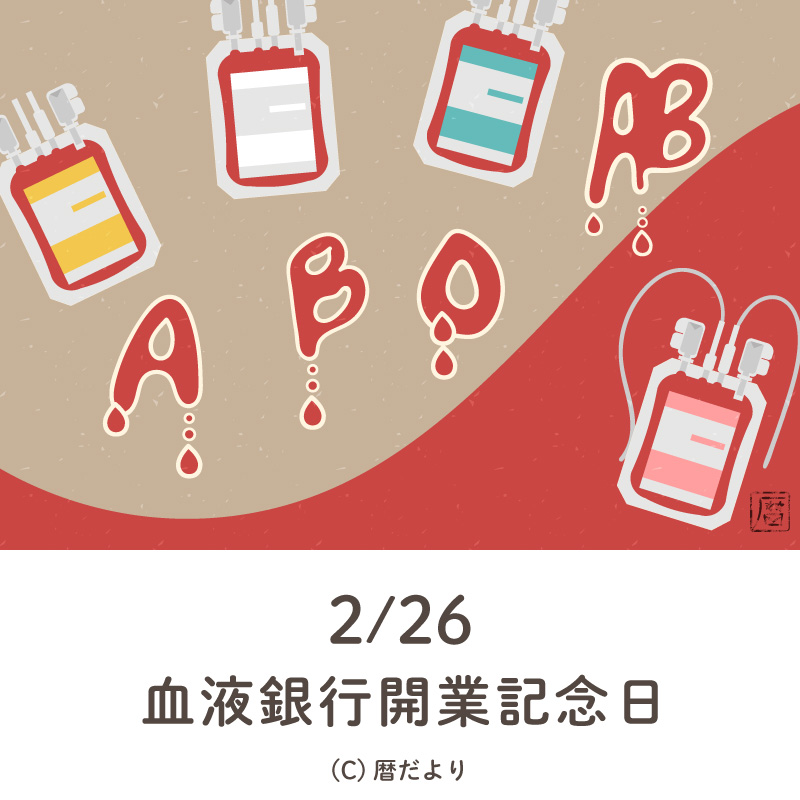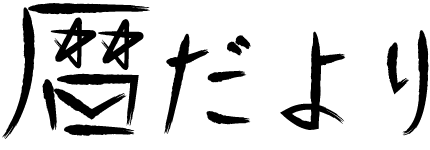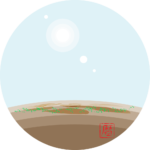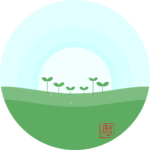二月の異名(和風月名)
寒さが厳しい時期で、さらに重ね着をする「衣更着(きさらぎ)」という意味があります。「如月」という漢字は、中国の2月の異名「如月(にょげつ)」が由来となっていて、寒い冬が終わり、春に向かって万物が動き始める時期という意味があります。
- 来更来(きさらぎ)
- 気更来(きさらぎ)
- 衣更着(きさらぎ)
- 草木張月(くさきはりづき)
- 小草生月(おぐさおいづき)
- 殷春(いんしゅん)
- 仲春(ちゅうしゅん)
- 初花月(はつはなつき)
- 梅見月(うめみつき)
- 梅津月(うめつづき)
- 梅津早月(うめつさつき)
- 木の芽月(このめつき)
- 雪消月(ゆききえつき/ゆきげづき)
- 令月(れいげつ)
- 恵風(けいふう)
- 雁帰月(かりかえりづき)
二月の節気
二十四節気
立春
【2月4日頃~2月18日頃】寒さもピークとなり、少しずつ春の兆しが現われてくる頃
雨水
【2月19日頃~3月5日頃】降る雪が雨へと変わって、雪解けが始まる頃
雑節
節分

立春前日(2月3日頃)
旧暦において立春が一年の始まり。その前日は大晦日にあたる特別な日として、邪気を祓う清めの行事が行われるなど大切にされた。
「節分」とは、もとは「季節を分ける日」のことで、立春・立夏・立秋・立冬の前日をさしていました。なかでも立春は、旧暦においては一年の始まり。その前日は大晦日にあたる特別な日として、年越しの祓い清めの行事が行われるなど特に大切にされました。そうして立春前日だけが節分とされるようになり、今日に至ります。
鬼やらい(追儺)
節分は、中国の宮中で年末に行われていた、「鬼やらい(追儺)」という疫鬼を追い出す儀式が伝わったものです。当時は豆をまく風習はなく、鬼役となった方相氏(金色の四つの目の面をつけ、右手に矛、左手に盾を持つ)を、桃の枝の弓と葦の矢で追い払うというものでした。日本では、陰陽道の行事として取り入れられ、毎年大晦日に朝廷でおこなわれていました。
豆まき
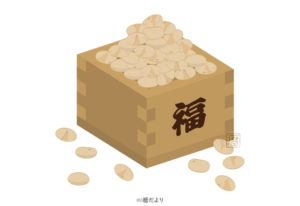
宮中で行われていた「鬼やらい(追儺)」は、室町時代以降に形を変えて現在の「豆まき」の行事となりました。
昔は五穀(稲、麦、粟、稗、豆)には生命力があり、それゆえ魔除けの力をもつと考えられていました。なかでも豆は、魔を滅する「魔滅」や、鬼の目を打って退治できるとして「魔目」などの漢字があてられ、社寺では豆を打ち付けることで邪気を祓う「豆打ち」という行事が行われました。これが中国から伝わった追儺の儀式と融合して、節分の「豆まき」となっていったようです。
また農村部には豊穣祈願として畑に豆をまく「予祝行事」がありました。邪気払いとしての豆打ちと、農事の始まりを予祝する豆まきの行事があわさって「祓いと予祝の行事」となり、「鬼は外、福は内」と唱えながら豆をまく節分行事として一般に広く行われるようになりました。
豆まきのやり方

節分前日、「福枡」に炒った大豆を入れて神棚に供えておきます。炒った大豆を使うのは、生の豆を外にまいた時に芽を出すことがあり縁起が悪いとされたため。また炒った豆が爆ぜる音も厄除けになりました。
節分当日の夜に、家じゅうの窓や戸を開けて、年男(その年の干支生まれの男性)か厄年の男性、または一家の主人が「鬼は外、福は内」と大きな声で唱えながら、家の内外に音を立てるように打ち付けて豆をまき、最後に勢いよく戸を閉めます。大声や威勢よく音を立てるのも魔除けの意味があります。
豆まきが終わったら、家族それぞれが自分の年の数(または数え年で一つ多く)の豆を食べます。この豆は「年取り豆」などと呼ばれ、食べながら一年間の無病息災を祈ります。
お年寄りは数が多く食べるのが大変なので、年の数の豆に熱いお湯を注いで「福茶」として飲んでも、同じご利益を得られるといわれています。
鬼

鬼は、「隠」または「陰」から変化したという説が有力で、元は具体的な姿はありませんでした。形の見えない病気や災いといった人間の想像できないような出来事を「鬼の仕業」と言うなど、恐れを表す言葉でした。(鬼は神様が姿を変えて現れたものや祖先の霊とされることもあります。)
陰陽五行説の思想では、鬼は「丑寅(北東)」という「鬼門(凶方角)」にいるといわれており、また十二支において「丑は冬、寅は春」とされることから、鬼は冬と春の境目に現れると捉えられていました。そのため冬から春に変わる立春前日の節分に鬼を祓う行事が行われるようになったのです。
ちなみに、鬼が牛のような角と、虎のような牙がある姿で描かれるようになったのも、鬼門が「丑寅」の方角であることに由来しているといわれています。
やいかがし(柊鰯)

節分は鬼を追い払う行事なので、鬼が嫌がるとされる「やいかがし」を、家の軒先や戸口、窓などに挿し置く風習もあります。「やいかがし」とは「焼き嗅がし」が転じた言葉で、焼いたイワシの頭をヒイラギの枝に挿したものです。「柊鰯」や「柊挿し」ともいわれます。
鬼はイワシの臭いが苦手とされており、またヒイラギの葉の棘は鬼の目を刺すことから、邪気が家に入ることを防ぐ魔除けの意味があります。
恵方巻

恵方巻は、節分の日に恵方を向きながら太巻きを一本丸ごと食べて、一年間の無業息災を祈る行事です。食べ終わるまで話してはいけないとか、目を閉じて願い事をしながら食べるとか、恵方巻の作法は様々です。
具材は七福神にちなんで7種類(かんぴょう、卵焼き、しいたけ、でんぶ、きゅうり、高野豆腐、穴子など)とされ、巻き寿司にするのは「福を巻き込む」という意味があります。
起源には諸説ありますが、江戸時代から明治時代にかけて、大阪の商人や芸子が商売繫盛や無病息災などを願い、節分に太巻き寿司を食べたのが始まりとされています。
昭和初期に大阪のお寿司屋さんが販促活動をしたのがきっかけで一般にも普及し始め、1989年にセブンイレブンが非関西圏の店舗で恵方巻を販売したところ売れ行きが好調だったことから、その後関西圏以外のコンビニやスーパーでも広く扱われるようになり全国に普及していきました。
二月の行事と暮らし
行事・暮らし
初午

2月最初の午の日
初午は、稲荷の祠に御神酒や油揚げなどを供える稲荷神社の祭礼。
和銅4年(711年)の初午の日に、祭神が伊奈利山に降臨したという稲荷大社(京都府伏見)の縁起にちなんだ祭礼です。商売繫盛で有名ですが、五穀豊穣の神「宇迦之御霊神」を主祭神としています。賑やかなことが好きな神様とされ、初午は盛大にまつられるのが特徴です。
初午の日は、稲荷の祠に御神酒や油揚げなどを供えます。油揚げを供えるのは、稲荷の使いとされている「狐」の好物だからです。
初午いなり

初午の日に「いなり寿司」を食べると福を招くといわれています。また関東は四角で酢飯、関西は三角で五目など、いなり寿司の形や具材は地域によって違いがあります。
稲荷の使い「狐」

狐は古くから霊的な動物と考えられていましたが、稲荷神社の祭神が仏教の荼枳尼天と混同されて習合したことにより、荼枳尼天の使女であった狐が、稲荷の使いとされるようになりました。
また農村部には「田の神様」という信仰がありますが、田の神様は「農業が始まる春に山から下りてきて、秋に山に戻る」とされていました。
狐も、春になると山から下りてきて田畑の害獣であるネズミを捕まえ、秋になると山に戻っていく習性があります。また人里近くまで来るものの人には決して近付かない様子にも神秘性を感じたようで、狐を田んぼの神様とすることもありました。
こうした田の神とキツネの信仰もあって、次第に稲荷とキツネを同一視するようになり「キツネ=お稲荷さん」のイメージが広く定着していったといわれています。
初午と習い事
また初午は、子どもの習い事を始めるのに良い日とされ、江戸時代には初午に寺子屋や私塾へ入門するという風習もありました。
針供養
2月8日
針仕事を休んで、使えなくなった針を集めて供養する日。
使えなくなった針を集めて、豆腐や大根、こんにゃくなどやわらかいものに刺して寺社に納め、感謝と同時に裁縫の上達を祈願します。
針供養は、「事八日」に行うものとされ、一般的には2月8日とされていますが、地域によっては12月8日に行われます。
事八日
正月をはさんだ12月8日と2月8日の両日を「事八日」といいます。このうち一方を「事始め」もう一方を「事納め」と言います。
「事」とは神事や農事のことです。12月8日を事始めとする地域では、正月を中心とする祭事を「事」とし、2月8日を事始めとする地域では、農作業の開始日という意味になります。
この「事八日」の両日は神を送迎する物忌みの日とされ、仕事を休んで家に籠らなければならないとされていました。
バレンタインデー
2月14日
日本では、女性から男性にチョコレートを渡して愛の告白をする日。海外では、大切な人へ贈り物をして愛や感謝を伝える日とされている。
キリスト教の聖人、聖バレンティノに由来する日です。古代ローマのキリスト教司祭だったバレンティノは、当時の皇帝クラウディウス二世が遠征する兵士の結婚を禁じたことに反抗し、多くの兵士を結婚させました。
そのためバレンティノは処刑されましたが、愛を守護する聖人とみなされ、その殉教の日である2月14日が「聖バレンティノの日」となりました。
ローマ国民が毎年「聖バレンティノの日」にお祈りをしていたものが、14世紀頃から「バレンタインデー」として恋愛に結び付けたイベントが行われるようになり、世界各地に広がったといわれています。
欧米では、家族や恋人が互いに花やカードを贈りあいます。
「チョコレートを贈る」という風習は日本独自のもので、1958年に東京のデパートで行われたキャンペーンが始まりでした。
1980年代になって「女性が男性にチョコレートを贈る日」「女性から愛の告白をする日」として定着したといわれています。
その後、時代の変化とともに義理チョコや友チョコなど新たな風習も加わって、現在のようなバレンタインデーとなりました。
祝日・記念日
国民の祝日
建国記念の日
2月11日
「建国をしのび、国を愛する心を養う。」と規定される国民の祝日。
元々は、初代天皇即位の初日を「日本の歴史が始まる最初の日(紀元)」とし「紀元節」という名称で祝ったのが始まりでした。戦後に廃止となりましたが、国民の意向により1967年に「建国記念の日」と名称を改めて再び祝日となりました。
日付は、古事記や日本書紀で初代天皇とされる神武天皇の即位日(辛酉年春正月庚辰朔)に由来しています。辛酉年春正月は旧暦1月1日で、グレゴリオ暦(新暦)により推定された日付が2月11日でした。
日本で「建国記念日」ではなく「建国記念の日」とされているのは、史実に基づく建国された日付を記念するものではなく、建国されたこと自体を記念する祝日だからです。
今日は何の日